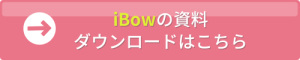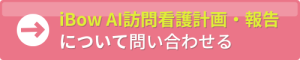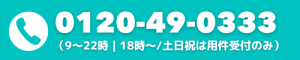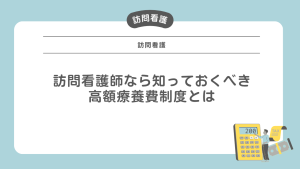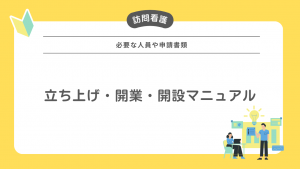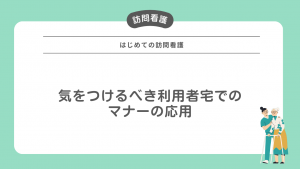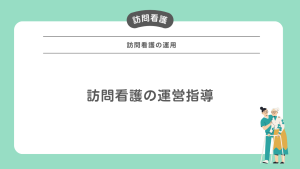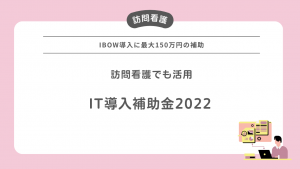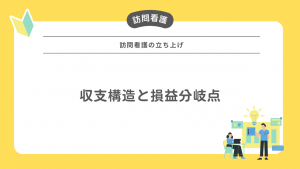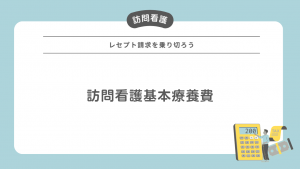訪問看護のスケジュール管理とシフト作成のポイントを徹底解説
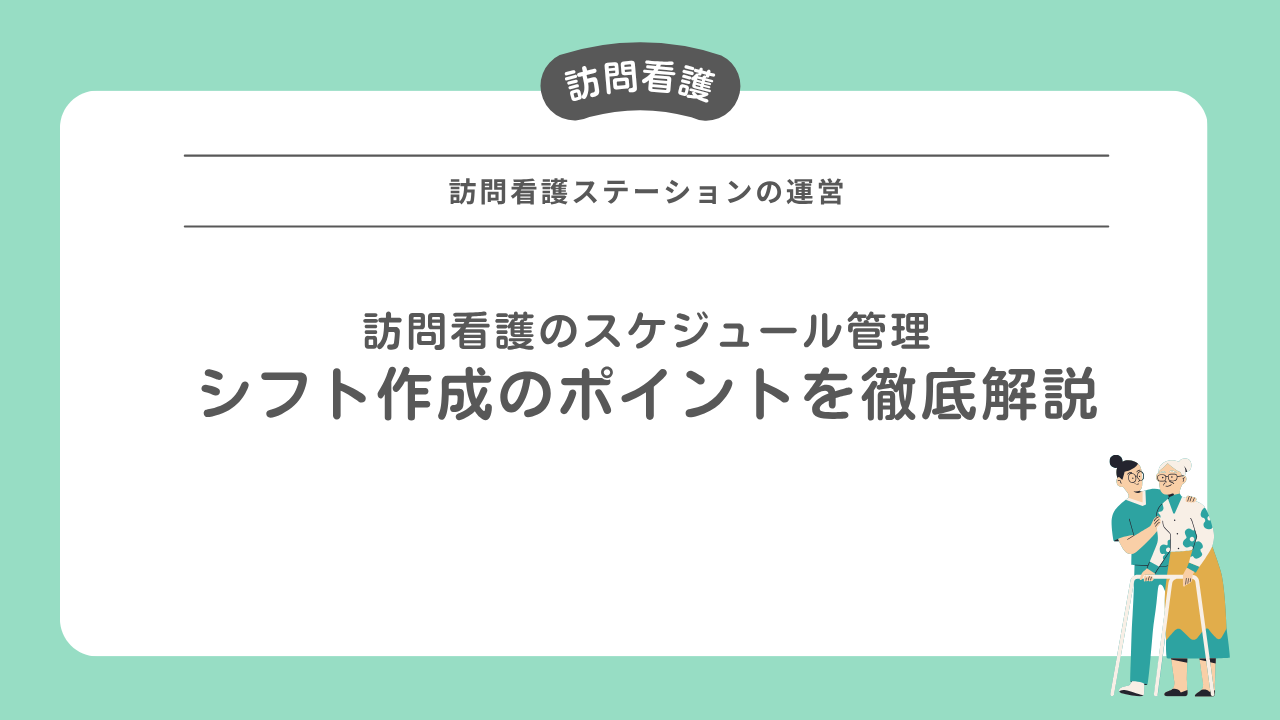
訪問看護の現場では、スタッフの働き方や利用者の生活リズムに合わせて、柔軟かつ効率的なスケジュール管理とシフト作成が求められます。1日に複数件の訪問がある中で、移動時間の最適化やオンコール対応、チーム内の連携まで、スケジュール作成には多くの配慮が必要です。この記事では、訪問看護における1日のスケジュール例から、無理のないシフト作成のポイント、効率化に役立つツールの活用方法までを詳しく解説します。
訪問看護の1日のスケジュール例
訪問看護師の一般的な1日の流れをはじめ、時短勤務やオンコール担当の場合のスケジュールをご紹介します。
一般的なスケジュール
9:00~18:00勤務の場合の一般的な流れをご紹介します。
| 9:00 | ■出勤・朝礼
事務所に出勤し、その日の訪問スケジュールを確認します。オンコールの有無や利用者の体調など、重要な事項を共有します。事務所によっては、自宅からの直行・直帰を基本とする場合もあり、その際は、オンラインでミーティングに参加します。 |
| 9:15~12:00 | ■午前の訪問
ミーティングが終了後、各自訪問に出発します。車や原付、自転車など、事業所によって移動方法は異なりますが、都心では自転車移動が多い傾向です。午前の訪問は2~3件ほどで、1件あたりの訪問時間は30分・60分・90分のいずれかが基本です。 |
| 12:00~13:00 | ■昼食・休憩
午前の訪問が終わったら、それぞれ昼休憩をとります。事務所で休憩することもあれば、飲食店などを利用することもあります。午前最後と午後最初の訪問先の場所によっては、事務所に戻らず、近くで休憩を取ることもあります。 |
| 13:00~17:00 | ■午後の訪問
休憩後、午後の訪問に出発します。訪問件数は2~4件ほどです。 |
| 17:00~18:00 | ■記録・終礼
最終訪問後は事務所に戻り、訪問記録の作成や必要な連絡を行います。終礼では、当日の共有事項や明日の予定などを確認します。訪問の合間に記録作成やチャットでの情報共有が進められるため、残業はあまり発生しない傾向にあります。 |
時短勤務の場合のスケジュール
時短勤務は、育児や介護などの事情がある人が、原則として1日6時間までの勤務が可能になる制度です。ただし「原則6時間」とされているものの、実際の働き方は事業所によって異なります。例えば、週5日勤務で1日6時間働くケースや、週4日勤務で1日8時間働くケースなど、勤務パターンはさまざまです。また、勤務時間によって休憩時間の扱いが異なるため、以下の点にも注意が必要です。
- 6時間勤務:法律上は休憩を設ける義務はありません
- 6時間超~8時間以下の勤務:休憩45分が必要
- 8時間勤務:休憩1時間が必要
6時間勤務の場合、法的には休憩は不要ですが、昼食時間をまたぐ勤務が多いため、休憩を取ってもらう方が安心です。以下は、6時間勤務かつ45分の休憩を取る場合の一例です。
| 9:00 | ■出勤・朝礼
事務所に出勤し、その日の訪問スケジュールや共有事項を確認します。 |
| 9:15~12:00 | ■午前の訪問
2~3件ほど訪問します。 |
| 12:00~12:45 | ■昼食・休憩
事務所や近隣の飲食店などで昼食をとります。 |
| 12:45~15:00 | ■午後の訪問
2~3件ほど訪問します。 |
| 15:00~15:45 | ■記録・連絡
訪問記録の作成や、必要な報告・連絡などを行います。 |
| 15:45 | ■退勤
1日の業務を終え、退勤します。 |
オンコール担当のスケジュール
24時間体制の訪問看護ステーションでは、看護師が交代でオンコール(夜間・休日対応)の当番を担当します。オンコール時は、事業所専用の携帯電話を持ち帰り、連絡があった場合に対応します。オンコール担当者は、必要に応じて電話対応や緊急訪問に出向くことがあります。
訪問看護におけるスケジュールの組み方のポイント
訪問看護のスケジュールは、ただ時間を埋めるだけではなく、利用者にとってもスタッフにとっても無理のない形で組み立てることが大切です。ここでは、スケジュールを組む際に意識しておきたい主なポイントをご紹介します。
利用者のスケジュールを考慮する
利用者は、訪問介護やデイサービスなど、他のサービスも併用していることがあります。その際は、利用者のスケジュールに影響のない日時に訪問看護を設定することが必要です。また、午前よりも午後に覚醒している利用者には、午後に訪問を設定するなど、1日の生活リズムにも配慮できると理想的です。
短い移動時間のルートで組み立てる
訪問スケジュールは、Googleマップなどのナビアプリを活用し、移動時間が短く済むような訪問ルートを組み立てることがポイントです。同じ地域に複数の訪問先がある場合は、まとめて訪問することで効率が上がります。また、通勤ラッシュや交通渋滞、道路の混雑状況なども考慮する必要があります。自転車での移動が中心の事業所では、危険な道路を避けた安全なルート設計も重要です。
1対1の受け持ち制をつくらない
1対1の担当制を採用すると、スケジュール調整の柔軟性が損なわれることがあります。例えば、担当スタッフが休暇を希望しても、利用者の状況によっては、代わりのスタッフによる訪問が難しくなる場合があります。また、精神的・身体的な負担が担当スタッフに偏ってしまうことも懸念点です。複数のスタッフで利用者を担当する体制をとることで、チーム内で知識とスキルを共有でき、看護ケアの質を高めることにもつながります。
利用者とスタッフの相性も考慮する
利用者とスタッフの相性も、スムーズな訪問ケアのために大切な要素です。お互いに無理のない関係性が築けるよう、相性に配慮しながらスケジュールを調整しましょう。必要に応じて、訪問スタッフの変更を検討することも大切です。
チームの調整力を高める
利用者やスタッフの状況によって、急なスケジュール変更が必要になることもあります。そのような場面に柔軟に対応するためには、チーム内で連携しやすい体制づくりが重要です。スタッフ同士が意見を出し合える、風通しの良い環境を整えておくことが、スムーズな調整力につながります。
訪問看護におけるシフト作成・管理のポイント
訪問看護のシフトでは、スタッフの働きやすさとサービス提供体制の両立が求められます。ここでは、訪問看護におけるシフト作成と勤務体制の管理で意識すべきポイントを解説します。
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表に沿って管理する
訪問看護では「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の作成が法律で義務付けられています。この一覧表をもとに、運営上の人員基準を満たしているか、各種加算の算定要件を満たしているかなどを確認し、適切に管理を行う必要があります。まずは一覧表に沿った運営を行うことが、事業所運営の基本となります。
スタッフの希望を考慮する
スタッフ一人ひとりの勤務希望や、育児・介護といった生活背景を把握し、可能な範囲でシフトに反映することは、モチベーションの向上につながります。ただし、すべての希望を反映することは難しい場合もあるため、その際はスタッフに理解してもらえるようなコミュニケーションを取ることが大切です。また、休暇の偏りが出ないように配慮し、公平性を保つことも重要です。
スケジュール作成、シフト管理の注意点
訪問看護の現場では、日々のスケジュール作成やシフト管理がサービスの質やスタッフの働きやすさに直結します。無理のないスケジュールと公平な業務分担を心がけることで、利用者への看護ケアの質を保ちながら、スタッフの定着やモチベーション向上にもつながります。ここでは、スケジュールやシフトを組むうえで意識しておきたい注意点をご紹介します。
タイトすぎるスケジュールは避ける
スケジュールが詰まりすぎていると、急いで訪問先に移動しなければならず、昼食や休憩が十分に取れないこともあります。その結果、移動中の事故リスクが高まったり、疲労によってケアの質が低下したりする恐れもあります。緊急訪問が発生するケースも想定し、余裕をもって移動・対応ができるよう、スケジュールにはゆとりを持たせることが大切です。
業務負担が偏らないようにする
オンコールの回数や訪問件数などが特定のスタッフに偏ると、心身の負担が大きくなります。業務量を公平に分散することで、スタッフ間の不満を防ぎ、チーム全体の働きやすさが向上します。また、業務の偏りを防ぐためには、「チーム全体で利用者を見る」という意識をスタッフに共有し、理解してもらうことも重要です。
訪問スケジュールやシフトの管理を効率化する方法
訪問日時は利用者によって異なるため、スケジュールやシフトの管理が煩雑になりがちです。口頭やオフラインの管理ではミスや伝達漏れが起きやすく、急な変更にも対応しづらくなります。そこで、誰でも使いやすいデジタルツールを導入することで、効率的かつスムーズな管理が可能になります。
Googleカレンダーでスケジュールを共有・編集する
Googleカレンダーは、スケジュールをリアルタイムで共有・編集できるツールです。各スタッフの訪問先や時間帯をカレンダーに記入することで、ダブルブッキングや予定の見落としを防ぐことができます。ただし、電子カルテと連動はできないため、入力の手間がかかります。また、誤入力のリスクがある点にも注意が必要です。
Googleスプレッドシートを活用する
Googleスプレッドシートは、スタッフの勤務日の集計や休暇希望の取りまとめなどに活用できます。休暇希望で活用する際には、あらかじめ入力用のフォーマットを用意し、提出期限を明確にしておくことで、スムーズに集計・調整が行えます。
便利で多機能な電子カルテ『iBow』を活用する
『iBow』は、スケジュール管理機能が充実しており、訪問予定や研修だけでなく、スタッフ一人ひとりの業務状況まで管理できます。スタッフの空き時間がひと目で把握できるため、ステーション全体のリソースを確認しながら、業務の割り振りやスタッフ間の連携がスムーズに行えます。また、個人のプライベート予定も管理できる機能があり、ワークライフバランスを考慮したスケジュール調整も可能です。現場全体の効率化だけでなく、スタッフの働きやすさにもつながるツールといえるでしょう。
効率的なスケジュール作成・シフト管理も『iBow』でできる
『iBow』は、利用者登録・記録・レセプト作成などの基本機能に加え、AIによる計画書・報告書作成サポートで、煩雑な書類業務効率化し看護業務に集中できる環境づくりを支援。さらに訪問予定やルートを自動作成できるようになります。利用者の住所・訪問時間・要件、スタッフのスキルや稼働状況をもとに、最適なスケジュールとルートを提案。移動時間を短縮し、偏りのないスタッフ配置が可能になるため、急な欠勤や緊急訪問にも柔軟な対応ができるようになります。属人化を防ぎながら、誰でも訪問できる体制づくりを支援するiBowのサービス詳細は製品資料をご覧ください。
iBow AI訪問看護計画・報告は、計画書・報告書のベースをAIが作成し、最終的に看護師の目でチェックすることで、今よりも短時間で高品質な計画書・報告書の作成が可能に。さらにiBow AI訪問看護計画・報告はリハビリ訪問にも対応し、別添リハビリ報告書も自動で作成できます。看護・リハビリ両方の情報を一貫して管理でき、作業時間の短縮と業務の効率化を実現!
お問合せいただいた方にiBow AI訪問看護計画・報告で作成した計画書・報告書のサンプルをプレゼント中!iBow AI訪問看護計画・報告について詳しく知りたい方はぜひお問合せください。
まとめ
訪問看護におけるスケジュールやシフトの管理は、スタッフの働きやすさと、利用者への安定したサービス提供の両立を実現するために重要な業務です。無理のないスケジューリング、チーム全体でのフォロー体制、そしてデジタルツールの活用を組み合わせることで、現場の業務効率とケアの質は大きく向上します。利用者のニーズに応えられる働きやすい現場を目指して、柔軟な仕組みづくりを目指していきましょう。
 お役立ち情報
お役立ち情報