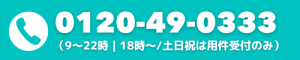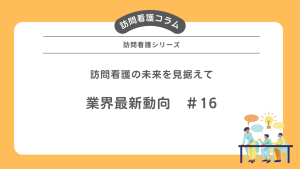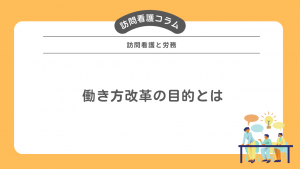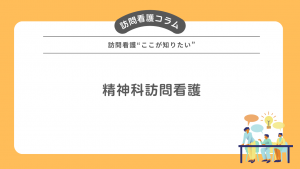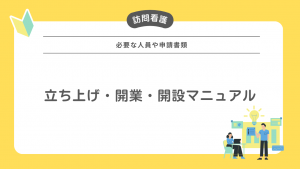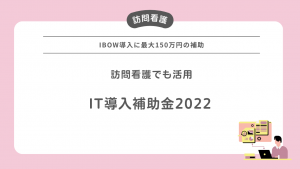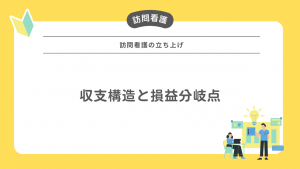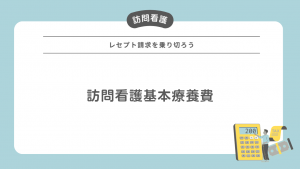訪問看護の未来を見据えて:業界最新動向#7
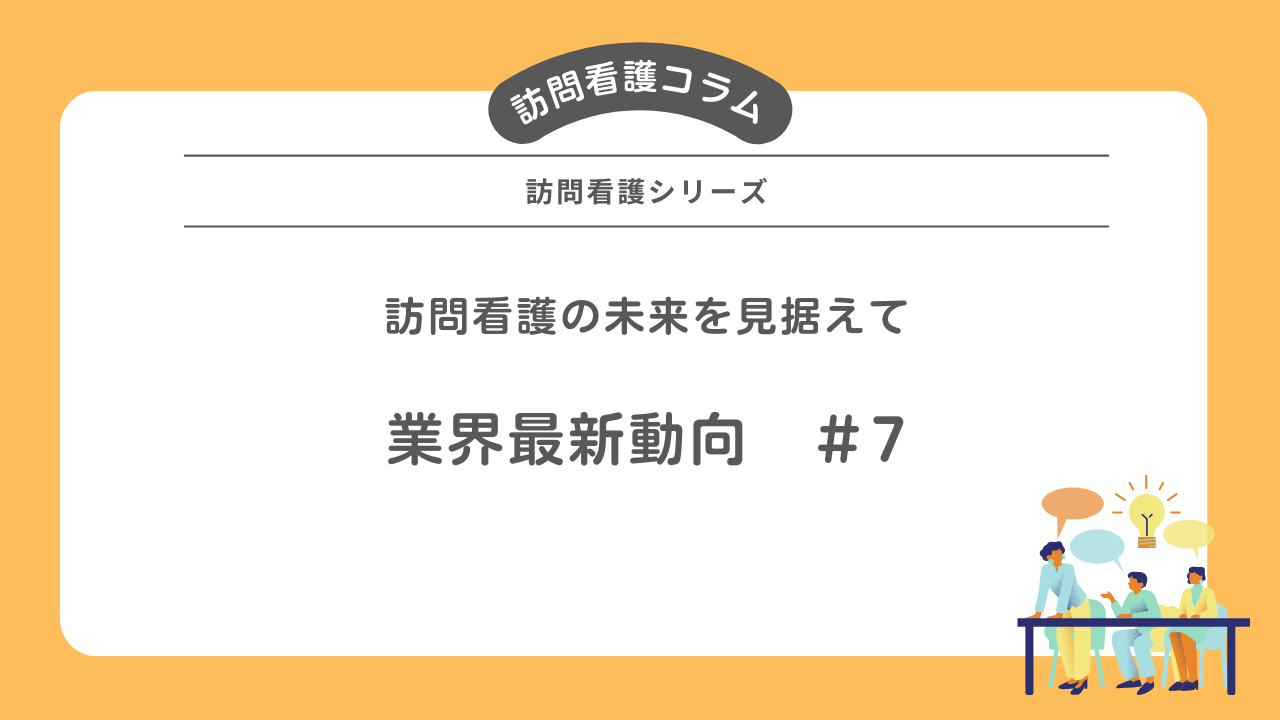
本コラムでは訪問看護業界に関わる最新の動向を探っていきます。今回のテーマは訪問看護の法定研修にも取り上げられている「高齢者虐待」に関して取り上げます。
高齢者虐待数 前年比31.2%増 3月末までに研修未実施の場合は報酬減算
厚生労働省は2024年12月27日、2023年度の高齢者虐待件数を発表しました。介護保険サービス従事者による虐待に関する相談・通報件数は前年比23.1%増の3,441件、このうち虐待と判断されたのは前年比31.2%増の1,123件で、いずれも過去最多です。 虐待の種類では、身体的虐待が51.3%と最も多く、以下、心理的虐待、介護放棄、経済的虐待、性的虐待と続きます。
虐待が増えている背景には、「どのような行為が虐待に該当するのか」という点が以前に比べて明確になり、これまでは見過ごされてきた虐待が表面化したことや、職員や家族などが行政などに虐待を相談・報告しやすい社会になっていることなども挙げられます。 しかし、今回の厚生労働省の発表では、虐待の発生要因は「職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意識の不足」が77.2%で最も多く、以下「職員のストレス・感情コントロール」「職員の倫理観・理念の欠如」となっているように、教育や本人の資質の部分が大きく影響していると思われます。
特に近年は人手不足による業務過多や、感染症予防対策、各種ハラスメントなどでストレスがたまりやすい環境と言えます。「虐待は絶対にしてはいけない」という意識付けを研修などで徹底させるとともに、働き方改革などを進めて心身の負担軽減を図っていくことも重要になります。
2024年の介護報酬改定では「高齢者虐待防止未実施減算」が新設されました。もちろん訪問看護事業者も対象です。 この減算は下記の4つの措置のうち1つでも欠けている場合には、実際に虐待が発生していなくても対象となります。
|
このうち、3については、2025年3月31日までが『報酬改定1年以内』なので、現時点では未実施でも仕方がない』と事実上の猶予期間が設けられています。しかし、それ以降は減算の対象として、自治体の運営指導でも細かくチェックされます。 「具体的にどのような研修をしなくてはいけないか」といった点までは規定されていませんが、朝礼時などでの口頭での指導・注意だけでは「実施した」という証拠がありません。必ず文書・動画など記録に残るツールを使って行う必要があります。
まとめ
特に訪問看護は、他者の目が届きにくい場所での業務が多いため「虐待が起こりやすい」「起こっても気づきにくい」環境と言えます。減算に関係なく、虐待防止対策は必須です。まだ研修を行っていない事業所は、必ず3月31日までに、全職員に対して記録が残るような形で実施しましょう。
 西岡一紀(Nishioka Kazunori) 西岡一紀(Nishioka Kazunori)フリーライター1998年に不動産業界紙で記者活動を開始。 2006年、介護業界向け経営情報紙の創刊に携わり、発行人・編集長となる。 2019年9月退社しフリー転向。現在は、大阪を拠点に介護業界を中心に新聞・会報誌・情報サイトでのインタビューやコラム執筆で活動中。 |
 お役立ち情報
お役立ち情報