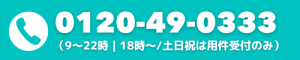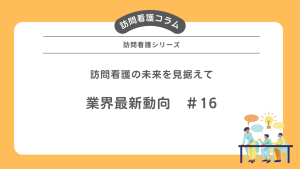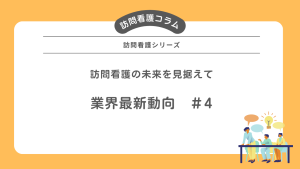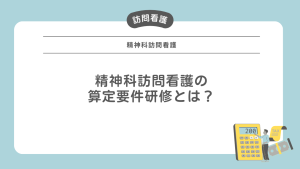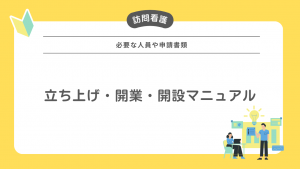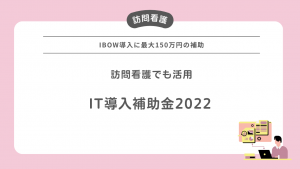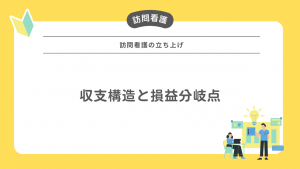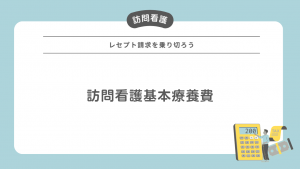介護業界最新動向13
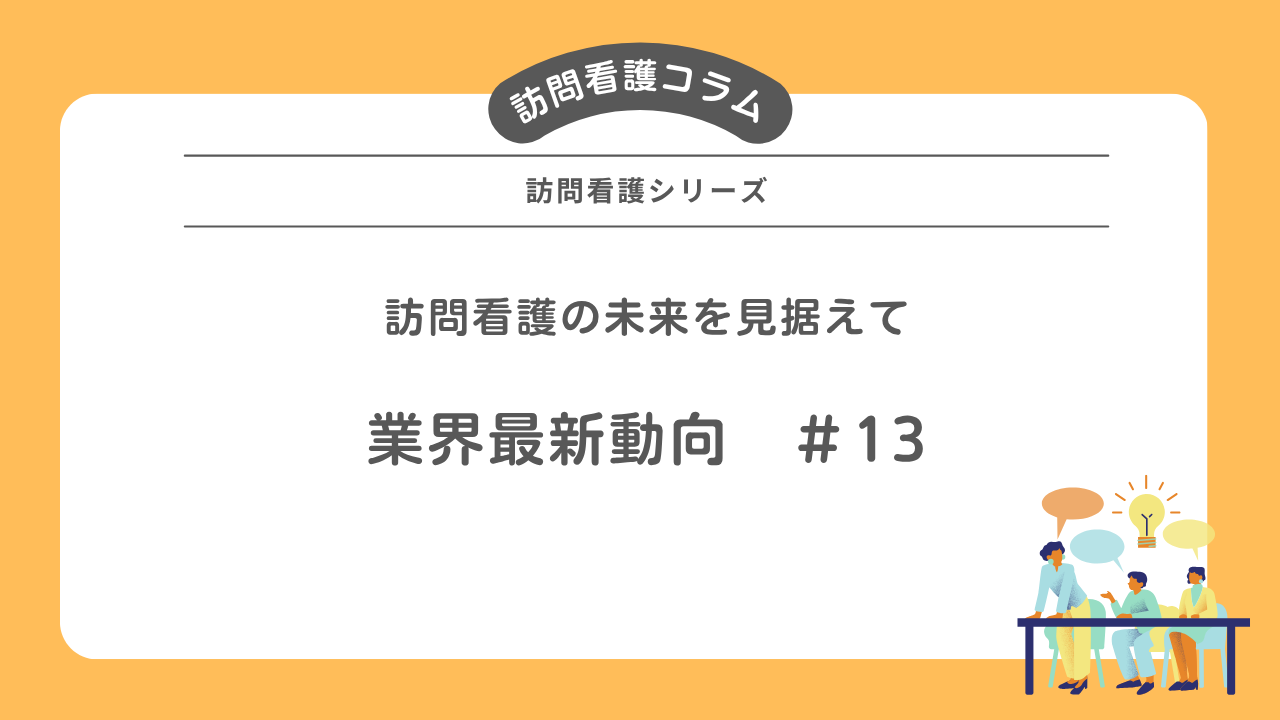
本コラムでは訪問看護業界に関わる最新の動向を探っていきます。今回は訪問看護ステーションにおけるカスタマーハラスメントの状況調査結果について取り上げます。
訪問看護事業所の6割がカスタマーハラスメント経験 離職防止のためにも対策が急務
2025年4月に訪問看護事業所の管理者2,628人を対象に行われたカスタマーハラスメントの状況調査によると「カスタマーハラスメントを受けた」という報告をスタッフから受けたことがある」との回答が64.2%にも達しました。4月には大阪市で訪問看護師が利用者に切りつけられるという危険な事態も発生しており、スタッフの安全確保は訪問看護事業所にとっては喫緊の課題と言えます。
「実際に報告を受けたハラスメントの内容」(複数回答)は、「威圧的な言動」が最も多く、以下「精神的な攻撃」「性的な言動」「執拗な(継続的な)嫌がらせ」などと続いています。こうしたハラスメントが起こる背景としては、まず「1対1、もしくは1対多数という状況で看護師が訪問するため味方や頼れる人が近くにいない」という業務形態が挙げられます。また、訪問看護師の多くが女性という点もハラスメントにつながっている可能性が考えられます。これを防ぐには複数名での訪問(できれば男性を含む)が望ましいのですが、現在の報酬体系下では全ての利用者に対してそれを実施するのは非現実的でしょう。また「利用者本人や家族が『訪問看護とは何か』を十分に理解しておらず、過剰なサービスを期待している」ということも考えられます。例えば、一般的には看護師・医師などの医療従事者は「病気やケガを治してくれる人」と認識されています。しかし、訪問看護などの在宅医療においては、そうした積極的な治療行為ではなく疼痛緩和などが主目的のこともあります。本人・家族がこの点を十分に認識していないと「ちっとも症状が良くならない。腕が悪い、本当に看護師か?」などといったハラスメントにつながる可能性が高くなります。
今回の調査では「ハラスメントを受ける可能性が高い要因」を複数回答で挙げてもらっていますが、その中には前述したような理由に加え、訪問看護事業所側の問題と思われるものもありました。例えば「提供するサービスの範囲やルールが統一されていない」です。ホスピタリティや使命感にあふれる訪問看護師が、良かれと思って本来の訪問看護の範囲を超えてしまうサービスをしていた場合には「前の看護師はしてくれたのに、なぜ今回はダメなのか」「ネット上に『訪問看護師がこんなサービスをしてくれた』という書き込みがあった」という無理な要求につながる可能性があります。また「マナーや対応方法などの教育・指導が不十分」という意見もありました。スタッフの研修をしっかりと行うことがハラスメントの抑止につながります。そのためにもICT化などで業務効率の改善を図り、人手不足の中でも教育・研修を行える時間を捻出するようにしましょう。
また「事業所を所管する自治体(保険者)で、カスタマーハラスメント相談窓口を開設しているかどうか」を尋ねたところ、46.4%が「わからない」と回答しています。このようにカスタマーハラスメントに悩みつつも、公的な補助や支援制度をきちんと把握しておらず、効果的な対策を講じることができていない現実が伺えます。補助・支援制度を周知するのは自治体の役目ではありますが、訪問看護事業所側も情報収集をしっかりと行っていく必要があるでしょう。
まとめ
カスタマーハラスメントはスタッフの離職にもつながるため、訪問看護事業所としては十分な対策を講じる必要があります。利用者や家族に「何がハラスメントに当たるのか」をしっかりと認識してもらい、そうした行為があった場合には毅然とした対応をとる旨を説明することが大事です。一方で、スタッフに対してもマナーに欠ける言動や曖昧・無責任な説明など、ハラスメントの要因を作らないよう、日頃から教育をしておく必要があります。また、合わせて自治体の補助・支援制度なども、しっかり確認しておきましょう。
 西岡一紀(Nishioka Kazunori) 西岡一紀(Nishioka Kazunori)フリーライター1998年に不動産業界紙で記者活動を開始。 2006年、介護業界向け経営情報紙の創刊に携わり、発行人・編集長となる。 2019年9月退社しフリー転向。現在は、大阪を拠点に介護業界を中心に新聞・会報誌・情報サイトでのインタビューやコラム執筆で活動中。 |
 お役立ち情報
お役立ち情報