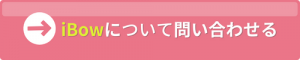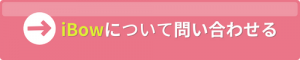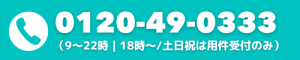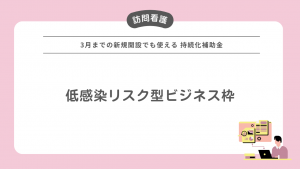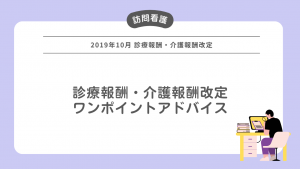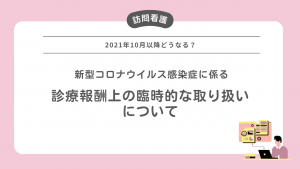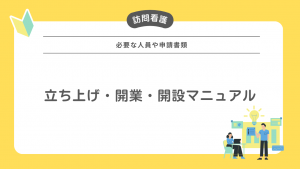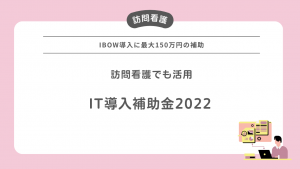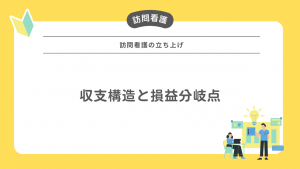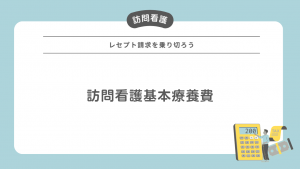訪問看護指示書!訪問看護が知っておきたい指示書の見方と返戻されない注意点とは?
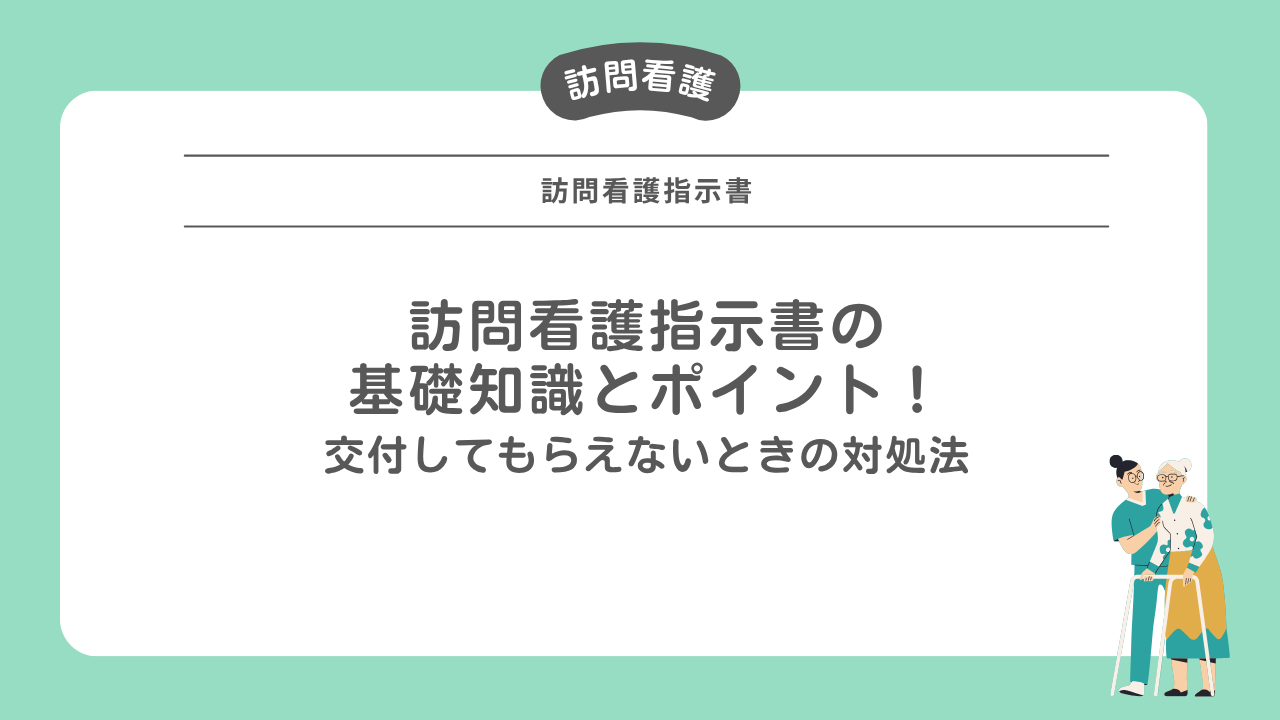
訪問看護を提供するにあたって欠かせない訪問看護指示書ですが、書類の不備や交付がスムーズに進まないなど、現場では意外とトラブルがつきものです。そこで今回は、訪問看護指示書の基礎的な知識から、届いた際のチェックポイント、交付されないときの対応法まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。
訪問看護指示書とは
訪問看護指示書は、在宅で療養する患者が訪問看護サービスを受ける際に、主治医が訪問看護ステーションなどの指定事業者へ交付する文書です。訪問看護指示書がなければ、訪問看護を提供することができません。訪問看護は介護保険、または医療保険にて提供しますが、いずれの場合も主治医の文書による指示が必要です。これは、介護保険法に基づく「指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準」や、健康保険法に基づく「指定訪問看護の事業の人員および運営に関する基準」により義務づけられています。訪問看護指示書には以下の内容が記載されます。
- 訪問看護指示期間(最長6か月)
- 基本情報(利用者の氏名、生年月日、住所)
- 主たる傷病名と傷病名コード
- 現在の状況(病状の状態、薬剤、ADL、介護度、褥瘡、装着・使用医療機器)
- 留意事項および指示事項
- 緊急時の連絡先や対応方法
- 特記すべき留意事項
- 他の訪問看護ステーションや、たんの吸引等実施のための介護事業所への指示の有無
- 医療機関名、医師名
訪問看護指示期間の記載が無い場合は、指示書の有効期間は1か月となります。とはいえ、記載が無い場合は主治医に連絡し、期間の記載を依頼すると安心です。
訪問看護指示書だけじゃない!指示書の種類を確認しよう
訪問看護指示書には、通常の訪問看護指示書の他、4つの種類があります。利用者の状況や疾患によって、どの指示書が交付されるかが異なります。
特別訪問看護指示書
特別訪問看護指示書とは、利用者の病状が急変した場合や退院直後など、通常よりも頻回な訪問看護が一時的に必要と主治医が判断した際に発行される指示書です。「週4日以上」の訪問看護が必要と医師が判断した際に発行される指示書です。
指示書の有効期間
最長14日間、原則として1人につき月1回まで。「気管カニューレ使用中」や「真皮を超える褥瘡がある」場合は月2回まで交付可能です。
適用される保険
特別訪問看護指示書が交付されている期間中は、介護保険でなく医療保険が適用されます。
注意点
通常の訪問看護指示書が交付されていることが前提で、特別訪問看護指示書のみの交付はできません。また、特別訪問看護指示書には「なぜ頻回な訪問が必要なのか」という理由を明記してもらう必要があります。
在宅患者訪問看護点滴注射指示書
在宅患者訪問看護点滴注射指示書は、利用者が「週3回以上の点滴注射」を必要とする場合に、主治医が訪問看護ステーションへ交付する指示書です。
指示書の有効期間
最長7日間、必要があれば週ごとに何度でも交付が可能。
適用される保険
介護保険、医療保険どちらも適用可能。
注意点
在宅患者訪問看護点滴注射指示書の交付を受ける際は、通常の訪問看護指示書も必要です。なお、在宅患者訪問看護点滴注射指示書の様式は、通常の訪問看護指示書と同じものです。
精神科訪問看護指示書
精神科訪問看護指示書は、在宅で生活する精神疾患の利用者に対して、主治医(精神科を担当する医師)が訪問看護ステーションに交付する指示書です。
指示書の有効期間
最長6か月
適用される保険
医療保険
注意点
主たる傷病名に精神疾患が記載されている必要があります。認知症のみの場合は対象外となる場合があるため注意が必要です。看護師以外にも、作業療法士や精神保健福祉士、保健師の訪問が可能です。
精神科特別訪問看護指示書
精神科特別訪問看護指示書は、精神疾患を持つ利用者の容体が急変した場合や、短期間に集中的な訪問看護が必要と主治医が判断した際に交付される指示書です。通常の「精神科訪問看護指示書」よりも頻回な訪問が必要な場合に発行されます。ただし、特別訪問看護指示書のような、条件により月2回の交付はありませんので注意してください。
指示書の有効期間
最長14日間、1か月に1回まで
適用される保険
医療保険
注意点
精神科特別訪問看護指示書の交付を受ける場合は、精神科訪問看護指示書も必要となります。
訪問看護指示料はステーションでは算定できないので要注意

訪問看護指示料は、医師が訪問看護ステーションへ訪問看護指示書を交付した際に、医療機関が算定できる診療報酬です。通常の訪問看護指示書および精神科訪問看護指示書は月に300点、その他の指示書については月に100点が算定できます。なお、訪問看護指示料は医師が算定するものであり、訪問看護ステーションは算定できない点に注意が必要です。
訪問看護指示書が届いたら確認すべきポイント
訪問看護指示書に必要事項が記載されていない、あるいは誤りがある場合には、適切なケアの提供ができず、加算が算定できないこともあります。内容に不備や誤記がある場合は、必ず発行元の医療機関へ連絡し、修正を依頼しましょう。訪問看護指示書が届いた際は、まず内容をしっかりと確認することが大切です。ここでは、チェックすべきポイントについて詳しく解説します。
指示期間
訪問看護指示書の指示期間は1~6ヶ月と決まっています。しかし、6ヶ月以上を超えた期間を記入してしまうケースが発生することも事実です。この場合の訪問看護指示書は、無効となってしまいます。ただし、指示期間の記入がない場合は発行から1か月の指示期間になります。
| 例.「訪問看護指示期間(令和3年10月1日~令和4年4月1日)」と記載があった場合 開始日が令和3年10月1日であれば、最長で令和4年3月31日までが期間となります。「令和4年4月1日」だと6ヶ月を超えてしまっているので、無効となります。 |
記入するだけではありますが、間違いやすい項目です。期間に問題ないかはよく注意しておきましょう。
基本情報
利用者の氏名や住所、生年月日等を記載します。手元にある利用者の情報をそのまま記載すれば問題ありません。しかし「名前が似ている利用者がいて、名前の書き間違えをしてしまった」という間違いが発生する可能性もあります。記載後に誤りがないか確認する作業は、怠らないようにしましょう。
主たる主病名
利用者の主病名を記載する欄です。この項目の書き方によって、訪問看護の介入が医療保険なのか、介護保険なのかが決まるため、非常に重要な項目となります。とくにパーキンソン病のヤールの重症度分類と生活機能障害度や脊椎・脊髄疾患等の場合は、書き方によって医療保険か介護保険なのかが決まり、そこにかかる自己負担額が大きく変わってきます。トラブルになりやすい項目なので、必ず確認しましょう。
現在の状況(病状・薬剤)
現在の病状や服薬している薬剤について記載をしましょう。内服が多い利用者の場合、「投与中の薬剤の用量・用法」の欄にすべてを書き切れないこともあります。その時は別紙に記載をし、「投与中の薬剤の用量・用法」の欄には「別紙参照」と記載すれば問題ありません。
現在の状況(ADLの状況・褥瘡・医療機器)
ここに含まれる項目は次のとおりです。
- 日常生活自立度(寝たきり度)
- 日常生活自立度(認知症の状況)
- 要介護認定の状況
- 褥瘡の深さ
- 装着・使用医療機器等
各項目に設定されている分類基準があるため、それに沿って記入してもらいましょう。
留意事項及び指示事項
ここで注意してほしい箇所が「Ⅱ-1 リハビリテーション」の項目です。ここに指示内容の記載等がないと、リハビリ専門職が利用者を訪問することができません。また、令和3年の介護報酬改定によって「頻度の記載」も必要になったことにも注意してください。
緊急時・不在時の連絡先等
ここも特にルールはなく、それぞれの項目に沿って記入すれば問題ありません。ただ、「他の訪問看護ステーションへの指示」「たんの吸引等実施のための訪問介護事業所への指示」が必要となる場合、ステーション間等で情報や報告書の共有が義務となるため、記載漏れが起きないようにしましょう。
医療機関名(医師名)・依頼先
ここで注意してほしいのが「捺印」です。必要情報の記入に加え、原本であることを証明するために捺印されていることが望ましいとされています。指示書を記載した日付・医療機関名(住所・TEL・FAX含む)・医師名も、記載内容に誤りがないか今一度確認しましょう
指示書の有効期間
訪問看護指示書の有効期間は、1か月から最長6か月までと定められています。 6か月を超える期間が記載されている場合、その指示書は無効となるため注意が必要です。
| 例:「訪問看護指示期間(令和7年10月1日~令和8年4月1日)」と記載されていた場合 開始日が令和7年10月1日であれば、有効な指示期間は令和8年3月31日までとなります。令和8年4月1日までと記載されていると、1日オーバーしており、6か月を超えてしまうため無効となります。 |
主たる傷病名と傷病名コード
訪問看護指示書の「主たる傷病名」の記載内容によって、適用される保険が医療保険か介護保険かに分かれるため、非常に重要な項目です。特に以下のようなケースでは、表記の違いにより適用保険が変わり、自己負担額も大きく異なるため注意が必要です。
| 傷病名の記載例 | 適用される保険 | |
| 皮膚がんの状態 | 末期の皮膚がん | 医療保険 |
| 皮膚がん(末期の記載なし) | 介護保険 | |
| パーキンソン病の分類と生活機能障害度 | パーキンソン病 ・ホーエン・ヤールの重症度分類Ⅲ度以上 ・生活機能障害度がⅡ度以上 |
医療保険 |
| パーキンソン病 ・上記の分類や障害度以外 ・ホーエン・ヤールの重症度分類・生活機能障害度について記載なし |
介護保険 | |
| 頚髄か頸椎か | 頚髄損傷 | 医療保険 |
| 頸椎損傷 | 介護保険 |
また、2024年度の診療報酬改定により、主たる傷病名には傷病名コードの記載も必須となりました。記載された傷病名に対して、正しいコードが入力されているかを確認しましょう。コードの検索には、厚生労働省の「傷病名マスター検索」の活用が便利です。
現在の状況(投与中の薬剤の用量・用法)
現在の状況にある「投与中の薬剤の用量・用法」では、薬剤の一覧が別紙に記載され、「別紙参照」となっているケースもあります。その場合は、別紙が添付されているかどうか、内容に漏れがないかを必ず確認しましょう。
現在の状況(ADLの状況・褥瘡・医療機器)
訪問看護指示書には、利用者の現在の状況として以下の項目が記載されています。
- 日常生活自立度(寝たきり度)
- 日常生活自立度(認知症の状況)
- 要介護認定の状況
- 褥瘡の深さ
- 装着・使用医療機器等
これらの項目について、該当する状態に○がついているかを確認しましょう。
特に注意すべき「褥瘡の深さ」
現在の状況で特に注意が必要なのは「褥瘡の深さ」です。以下のようなケースでは、訪問看護指示書に「真皮を超える褥瘡」であることが明記されている必要があります。
- 特別管理加算を算定する場合
- 特別訪問看護指示書(月2回交付)を使う場合
「真皮を超える褥瘡」とは、以下の分類に該当する状態を指します。
| 分類 | 内容 |
| NPUAP分類 Ⅲ度 | 全層組織損傷(脂肪層まで損傷) |
| NPUAP分類 Ⅳ度 | 全層組織欠損(筋肉・骨まで達する損傷) |
| DESIGN-R 2020分類 D3 | 皮下組織までの損傷 |
| DESIGN-R 2020分類 D4 | 皮下組織を超える損傷 |
| DESIGN-R 2020分類 D5 | 関節腔・体腔に至る損傷 |
上記の等級が指示書に明記されていることが必須条件となるため、しっかり確認しましょう。
留意事項及び指示事項
リハビリ専門職による訪問看護が必要な場合、「Ⅱ-1.理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護」の記載が必須です。リハビリの1日あたりの時間と週の回数、指示内容が記載されているかを確認します。
他の訪問看護ステーションや介護事業者を併用している場合
利用者が複数の訪問看護ステーションを利用している場合は、「他の訪問看護ステーションへの指示」の「有」に〇、該当ステーション名の記載が必要です。また、たんの吸引等の実施を訪問介護事業所が担っている場合には、「たんの吸引等実施のために訪問介護事業所への指示」の「有」に〇、事業所名の記載が必要です。
医療機関名(医師名)・依頼先
訪問看護指示書の下部には、指示書の記載日、医療機関名(住所・電話・FAX)、医師名が記載され、その医師の捺印があります。情報に誤りがないか、また捺印漏れがないかを必ず確認しましょう。特に医師の捺印漏れはよく見られます。たとえ指示書の内容がすべて正しく記載されていても、医師の印鑑がない場合はその指示書は無効となり、訪問看護サービスを提供することができません。
訪問看護指示書を交付してもらえない主な理由と対応法
訪問看護指示書は、主治医の判断によって交付されますが、状況によっては指示書を書いてもらえないケースもあります。 ここでは、考えられる理由と、それに対する対応方法を紹介します。
交付の必要性を感じていない
主治医に訪問看護の必要性が十分に伝わっていない場合、指示書を交付してもらえないことがあります。このような場合には、利用者やご家族の同意を得た上で、事業所から文書やFAXで主治医に情報提供することが有効です。病院での様子と自宅での生活実態にはギャップがあることも多く、「病院ではしっかりしているように見えるけれど、実は自宅では困りごとが多い」といったケースもあります。以下のような情報を主治医に伝えると、訪問看護の必要性をより理解してもらいやすくなります。
- 自宅での健康状態や生活の様子
- ご家族の支援状況や介護の負担
- 日々の生活で困っていること
- 訪問看護で提供できる具体的なサポート
- ケアマネジャーからの意見や支援の必要性
受診の間隔が空いている
利用者がなかなか受診できず、家族が代理受診していたり、外来受診の間隔が長く空いてしまったりすると、「本人の状態がわからないため指示書は書けない」と医師から断られることがあります。このような場合は、利用者に受診の必要性を説明し、受診を促すことが大切です。
主疾患を診ていない医師に依頼している
訪問看護指示書は、原則として主治医が作成するものとされています。そのため、主疾患を診ていない医師に依頼すると、「主疾患を診ている医師に書いてもらってください」と断られることがあります。また、訪問看護指示書は保険医療機関に所属する保険医であれば誰でも作成可能とされていますが、トラブルを避けるためには主疾患を診ている医師に依頼するのが確実です。
主治医が非常勤である、または多忙である
主治医が非常勤の場合、勤務日が限られているため、訪問看護指示書の作成が遅れることがあります。また、多忙な医師の場合、診療業務が優先され、指示書の作成に時間を割けないことや、作成自体を忘れてしまっているケースもあります。このような場合には、医療機関に連絡を入れてフォローしましょう。連絡するタイミングとしては、診察開始直後などの忙しい時間帯を避けると、スムーズに対応してもらえることが多いです。
関係者間のコミュニケーションがうまく図れていない
訪問看護を導入する際には、通常、利用者本人やケアマネジャーから主治医にその希望が伝えられますが、伝達の過程で情報が正しく伝わっていなかったり、意図が十分に共有されていなかったりすることがあります。また、医療機関の窓口担当者と医師との間での情報共有が不十分な場合、訪問看護指示書の作成依頼自体が医師にうまく届いていないケースも考えられます。このような場合には、改めて医療機関へ連絡し、依頼の経緯や訪問看護の必要性を丁寧に伝えることが大切です。事業所から書面で情報提供を行う、ケアマネジャーと連携して再度依頼するなどの工夫も有効です。下記の記事でも、訪問看護指示書を書いてもらえない場合の解決策について解説しているのでご参考ください。
指示書管理もスムーズに。事務作業を効率化する訪問看護専用電子カルテiBow

ここまで訪問看護指示書の見方の注意点やポイントを紹介してきました。訪問看護では、訪問看護指示書の管理や交付依頼など、医師や関係者との連携が欠かせません。iBowは指示書ひな形の搭載や有効期限リストの自動出力、交付依頼書の作成にも対応しており、期限切れの防止や依頼業務の手間を大幅に軽減できます。また、利用者の心身状態などの情報がレセプトに自動反映されるなど、細かな事務作業も効率化。看護師の現場負担を減らしつつ、書類の抜け漏れを防ぐサポート機能が充実!訪問看護の業務改善やシステム選びに迷ったらまずはiBowの製品資料をダウンロードしてみてください。
まとめ
訪問看護指示書は、利用者に適切なサービスを提供するために欠かせない文書です。内容に不備があると、必要なケアが実施できなかったり、加算が算定できなかったりする可能性があります。そのため、指示書が届いたらまずは内容をしっかり確認することが重要です。また、指示書が交付されない場合でも、情報提供の工夫や関係者との連携によって、状況が改善することは少なくありません。日頃から丁寧な確認と対応を心がけることで、よりスムーズで質の高い訪問看護の提供につながります。
 お役立ち情報
お役立ち情報