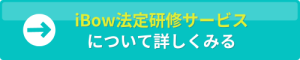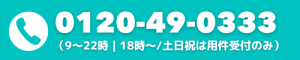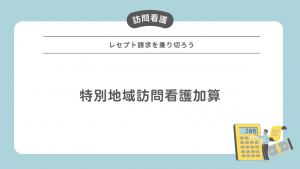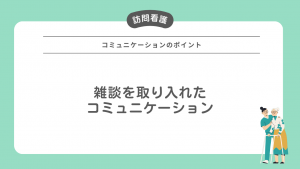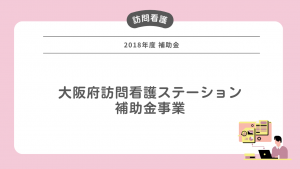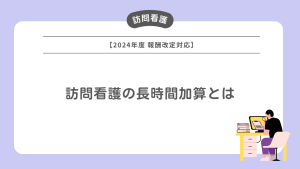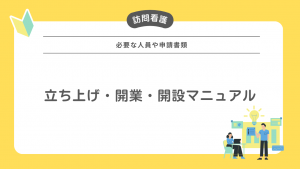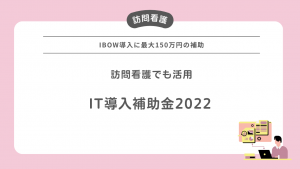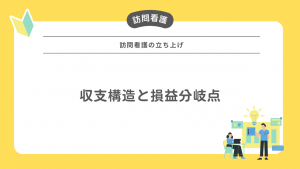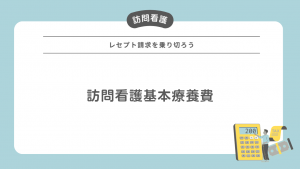訪問看護従事者なら知っておくべき!高齢者虐待防止に必須の取り組みや心構えとは?
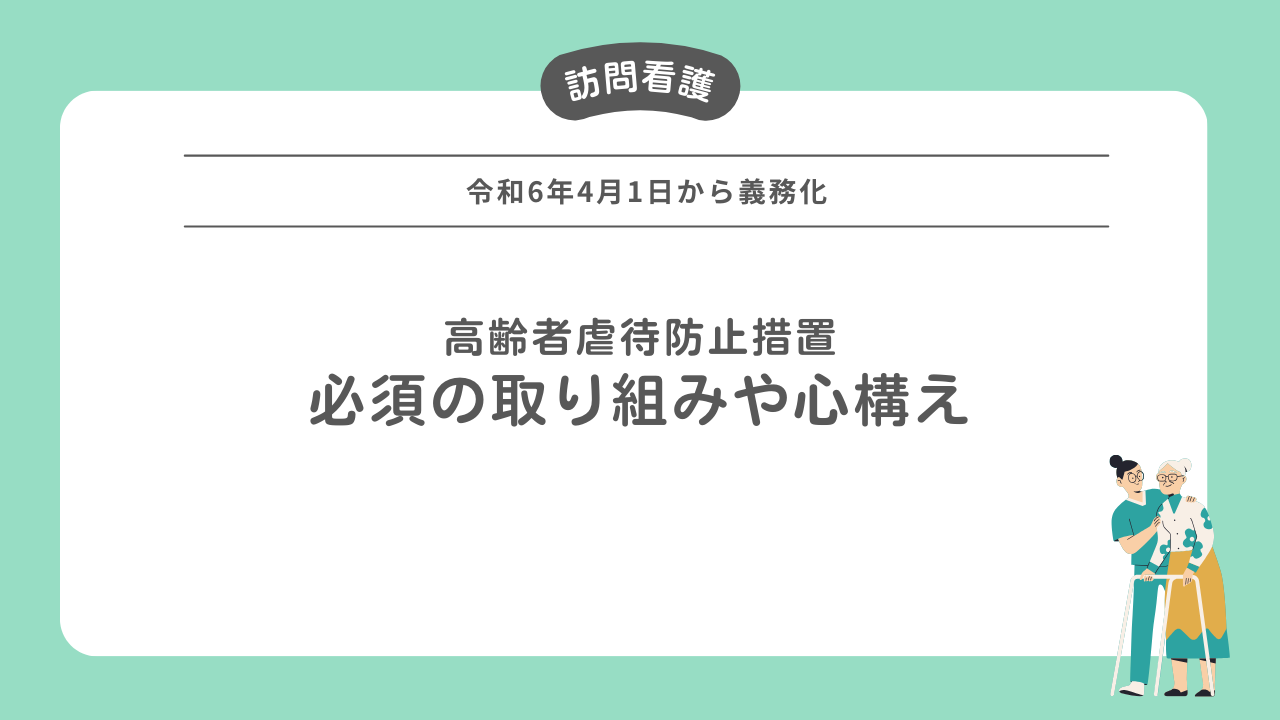
児童や高齢者への虐待、家庭内暴力(ドメスティック・バイオレンス:DV)が大きな社会的問題となってから年月が経った現在でも、被害相談等の件数は増加の一途を辿っています。訪問看護の場においても、そのような問題に接する場面があるため、虐待の実態とその予防的な介入について看護師が十分な認識と知識を持つ必要があります。今回の記事では、高齢者の虐待を防止するために必要な措置と虐待を防止していく上での心構えについて紹介します。
高齢者虐待防止法とは
高齢者に対する虐待については、2006年4月から「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援などに関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されています。
高齢者虐待防止法とは、高齢者虐待として「養護者による高齢者虐待」と「要介護施設従事者による高齢者虐待」を規定しています。前者は家庭内の虐待であり、実際に高齢者の介護や世話をしている養護者が、高齢者(65歳以上の者)を虐待している場合のことを指します。これに対して、後者は老人福祉法および介護保険法に規定された施設や事業の業務に従事している者(要介護施設従事者等)による虐待のことを指します。同法では、「養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合は、速やかにこれを市町村に通報しなければならない」と通報が義務付けられています。また、「それ以外の場合でも速やかにこれを市町村に通報するよう努めなければならない」とされています。この場合、守秘義務に関する法律の規定は、通報することを妨げるものと解釈をしてはいけません。通報を受けた市町村は、地域包括支援センターなどと連携協力体制を整備し、相談・指導・助言・養護者への支援などを行います。また、必要があれば高齢者の保護のために迅速に施設へ入所・転院をさせるなどの措置も行います。
高齢者虐待防止法に基づく体制整備の充実、取り組みの強化が令和6年4月1日から義務化
高齢者虐待の相談・通報件数および虐待判断件数は厚生労働省から出されている令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(報告)の概要によると増加傾向が続いています。 また、過去に虐待が発生した介護施設等においても虐待が再発する件数が増加傾向にあることから、令和3年度より厚生労働省から一層の対応の強化を行うように以下の通知が出されました。
| 運営基準改正における虐待防止規定の創設
○運営基準改正にて、全ての介護サービス事業者を対象に研修等の実施を義務付けた。 【主旨】 全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又 はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。 【1 基本方針 】 入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者 に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定。 【2 運営規程】 運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加。 【3 虐待の防止】 虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。 ① 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること ② 虐待の防止のための指針を整備すること ③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること ④ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと 【施行期日】 施行日:令和3年4月1日(施行日から令和6年3月31日までの間、経過措置を設ける) |
※引用:介護給付費分科会(第232回)その他【高齢者虐待の防止、送迎】(改定の方向性) 厚生労働省 社会保障審議会
運営基準改正における虐待防止規定の創設で定められた経過措置は令和6年3月31日で終了し、令和6年4月1日から義務化となりました。
高齢者虐待の範囲とは
虐待の類型としては、①身体的虐待、②介護・世話の放棄・放任、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の5つが定められています。
①身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴力を加えることを指します。
②介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ることを指します。
③心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応を示すなど、高齢者に著しい心理的外傷を与える態度や言動を行うことを指します。
④性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせることを指します。
⑤経済的虐待:養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、そのほか当該高齢者から不当に財産上の利益を得ることを指します。
訪問看護の運営基準を満たすために必須の措置・対策は?
令和6年度からの虐待防止に向けた対応強化の義務化に伴い、訪問看護事業所側では、虐待発生防止のために講じる措置を施行し、その内容について職員全体で共有を行うことが求められています。
①虐待防止対策検討委員会を定期的に開催すること
虐待防止に関する委員会を設置し、定期的な会議を実施していくことが必要です。例えば、虐待の事例に関する情報共有をしたり、日々の訪問の中で認知症の利用者などを対象に虐待が起こるリスクが生じていないか、養護者の介護疲れがみられないか、家族への支援や社会資源が十分に行き渡っているか、抑うつなどの訴えがみられないか等を話し合ったりします。このような積極的な意見交換の場を設けることで、虐待の早期発見や虐待防止に向けた対策の拡充に繋がることが期待されます。
② 虐待の防止のための指針を整備すること
事業者として、虐待防止に向けた具体的な行動の規範をスタッフに明確に示すことが必要です。まずはスタッフ自身の虐待防止における姿勢・態度についてどうあるべきか、虐待の早期発見・早期支援にはどのような視点が必要なのかを、企業理念や行動指針や日々のコミュニケーション等を通してスタッフ全員に伝達・共有することが大切です。スタッフが訪問時に1人で虐待を判断し対応するのではなく、複数の関係者がチームとなって対応することが虐待の早期発見・早期支援に繋がると考えられます。
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
事業所内で虐待防止に対する意識を高めるだけではなく、訪問スタッフが実際に虐待の相談を受けた場合や、訪問時に虐待を察知した時に十分な対応が行えるように、定期的な研修の実施が必要になります。このような研修は、地域の市町村や地域包括支援センター、他事業所が主体となって定期的に研修を主催している場合もあります。積極的に外部研修に参加することで、スタッフの虐待に関する知識が深まり、地域との情報共有・連携の強化にも繋がります。
④ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
事業所内で虐待防止の取り組みに関する担当者を配置することが必要となります。虐待に関する連絡・相談の窓口や、虐待防止対策検討委員会、虐待防止に関する指針の周知だけでなく、虐待に関する研修の企画や周知といった役割を担うことで、虐待防止に向けた具体的な行動を継続していくことに繋がります。
もし虐待を発見したらどのように対応すべきか?
高齢者虐待への対応の仕組みとして、在宅看護に携わる看護師等も含めて、高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見する努力義務が規定されています。しかし、在宅看護を担う者としては、高齢者虐待が発生する前段階で対応することが望ましいと考えられます。例えば、認知症による言動の混乱により、家族も混乱して疲労している段階で、高齢者や家族からの相談に応じ、助言をするなどして未然に虐待を防止することも必要です。
家族からの虐待が疑われる場合
家族または養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、市町村または市町村から委託を受けた地域包括支援センターに通報するよう努力する義務、または通報する義務(高齢者の生命や身体に重大な危険がある場合)が課されています。在宅看護においては、看護師が発見者となることも少なくないため、その場合は看護師が通報努力義務または通報義務を負うことになります。
実際には、事業所の管理者や虐待防止の担当者に速やかに情報を共有し、担当のケアマネージャー、介護士などサービス担当者間とも連携を取り、療養者と養護者から個別に聞き取りを行い、虐待の様子や経過を把握した後に市町村および地域包括支援センターに連絡を行います。この時に注意しておきたいのは、介護疲れなどで家族自身が何らかの支援を必要としている場合があることです。「被害者(高齢者)と加害者(養護者や家族)」という構図に基づく対応ではなく、家庭全体の状況からその家庭が抱えている問題を理解し、本人とともに家族を支援することが大切です。家族を責める口調で問い正すのではなく、ねぎらいの言葉をかけ、寄り添う姿勢を保つことが重要となります。
職員からの虐待が疑われる場合
要介護施設従事者や、高齢者の福祉に職務上関係のある者などから虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合にも、市町村に対する通報努力義務、または通報義務(自分が業務に従事している施設または事業における虐待の場合および高齢者の生命や身体に重大な危険がある場合)があります。職員による虐待を防止するために注意をしておきたいのは、虐待にいたる前段階において、職員の疲労や、ケアをする対象者との大小のトラブル、クレーム、ハラスメント等が生じている場合があることです。職員の性別や経験およびケアをする対象者とのこれまでの関わりなども考慮して、状況に応じてケアの可否や担当者の変更を検討し、お互いが安全な環境のもとで適切なサービスが提供できるように調整をしていくことが大切です。
運営指導に最適なiBow e-Campus
訪問看護においては、高齢者虐待防止措置のほかにも感染予防など様々な法定研修を定期的に実施することが義務付けられています。しかし、多忙な日常業務の中でこれらを適切に管理・運営することは容易ではありません。経過措置期間も令和6年3月31日で終了し、令和6年4月1日からは義務化となりました。訪問看護ステーションに勤務する全スタッフが毎年受講完了する必要があります。まだ法定研修の実施・受講が済んでいない場合は早めに受講完了まで進めましょう。
iBow e-Campus訪問看護 法定研修編は、オンラインでいつでも受講できるので、忙しい現場でも、スキマ時間をうまく活用し法令に基づいた研修を受けることができます。また、研修受講後は受講証明書の発行がされます。さらに、管理者は各スタッフの受講状況や進捗の確認ができるため運営指導で受講状況を求められた際にも慌てることなく対応していただけます。
まとめ
高齢者虐待防止を推進している中でも、未だに虐待の明らかな減少には至っていません。在宅での介護は長時間限られた空間の中で療養者と向き合うため介護疲れが蓄積しやすくなっています。しかし、現状は介護する家族への支援が十分に行き渡っていない場合も少なくありません。そのため、慣れない介護や普段行わなかった家事などに苦しんでいても、周りに助けを求められず、問題の深刻化や虐待発生に拍車をかけていると考えられます。高齢者虐待の予防や支援においては、療養者の安全を確保するとともに、家族・養護者にも寄り添い、支援する姿勢をもって関わることが大切です。
「高齢者虐待防止の推進」が、訪問看護従事者一人ひとりの、療養者と家族の尊厳を守るという意識を高め、虐待防止に向けた積極的な取り組みがさらに増えていくきっかけになればと思います。
 お役立ち情報
お役立ち情報