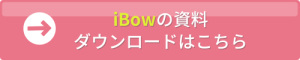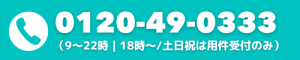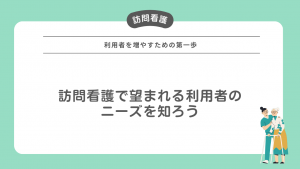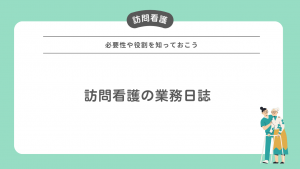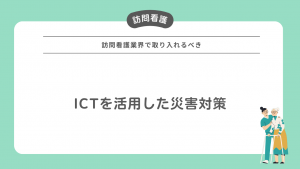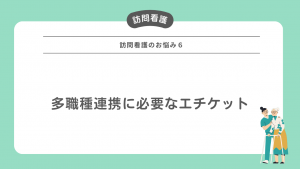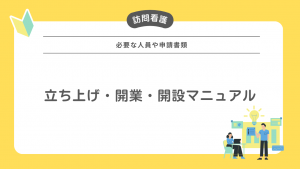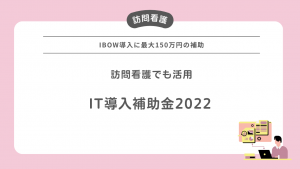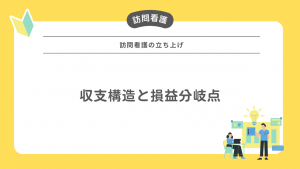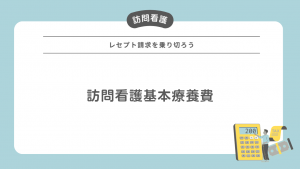訪問看護師なら知っておくべき、高額療養費制度とは
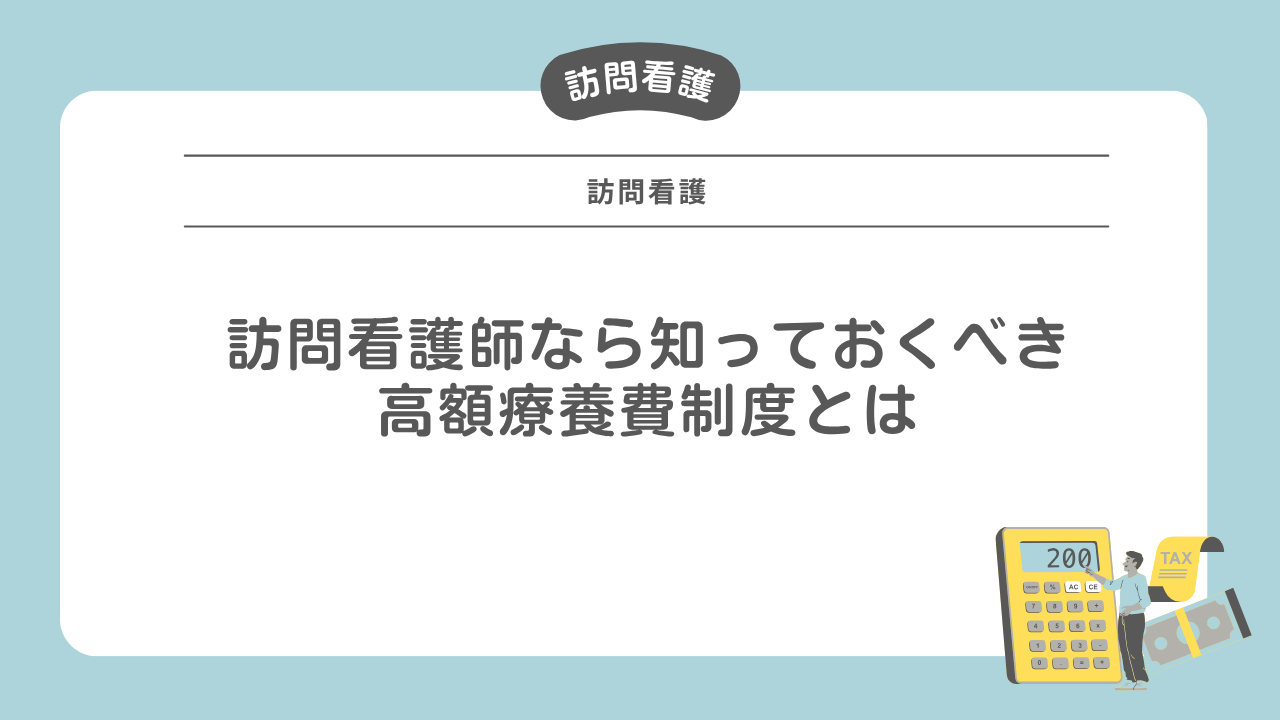
訪問看護の現場では、利用者やその家族から「医療費が高くて大変」「どんな支援制度が使えるの?」という相談を受けることが少なくありません。特に、慢性疾患や長期間の医療が必要な方にとって、高額な医療費は大きな負担となります。そんなときに役立つのが高額療養費制度です。本記事では、高額療養費制度の基本的な仕組みや上限額について分かりやすく解説します。あわせて、高額介護(介護予防)サービス費と高額医療・介護合算制度についても解説します。訪問看護師として、利用者の経済的負担を軽減するための知識を身につけ、より安心できるケアを提供しましょう。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が1か月の自己負担限度額を超えた場合、その超過した分を公的医療保険から支給する制度です。この制度は、医療費が家計を圧迫しないようにするために設けられました。ただし、入院時の食事負担や差額ベッド代、先進医療にかかる費用等は含みません。
高額療養費制度の支給要件
同じ月に支払った一部負担金や療養にかかった費用のうち、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費として支給される額を差し引いた金額(一部負担金等の額)が上限額を超えた場合、高額療養費が支給されます。
高額療養費制度の一月の上限額
過去12か月以内に、高額療養費の上限を3回以上達した場合、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。ただし、70歳以上で住民税非課税区分の場合は、多数回の適用はありません。また、70歳以上の場合、外来のみで適用される上限枠も設けられています。
70歳以上の方の上限額
1つの医療機関等での自己負担額(院外処方代を含む)が上限額を超えなかった場合でも、同じ月に他の医療機関等で支払った自己負担額と合算することができます。合算後の総額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
| 適用区分 | 外来(個人ごと) | 一月の上限額(世帯ごと) | |
| 現役並み | 年収1,160万円~ 標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% 多数回該当の場合:140,100円 |
|
| 年収約770万円~約1,160万円 標準報酬月額53万円以上 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% 多数回該当の場合:93,000円 |
||
| 年収約370万円~約770万円 標準報酬月額28万円以上 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% 多数回該当の場合;44,400円 |
||
| 一般 | 年収156万~約370万円 標準報酬月額26万円以下 課税所得145万円未満等 |
18,000円 (年上限144,000円) |
57,600円 多数回該当の場合:44,400円 |
| 非課税等住民税 | Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
| Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 | ||
69歳以下の方の上限額
1つの医療機関等での自己負担額(院外処方代を含む)が上限額を超えなかった場合でも、同じ月に他の医療機関等で支払った自己負担額と合算することができます。ただし、69歳以下の場合は、自己負担額が21,000円以上であることが必要です。合算後の総額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
| 適用区分 | 一月の上限額(世帯ごと) | |
| ア | 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% 多数回該当の場合:140,100円 |
| イ | 年収約770~約1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% 多数回該当の場合:93,000円 |
| ウ | 年収約370~約770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% 多数回該当の場合:44,000円 |
| エ | ~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 多数回該当の場合:44,000円 |
| オ | 住民税非課税者 | 35,400円 多数回該当の場合:24,600円 |
高額療養費制度の申請方法と期限
申請方法
加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に高額療養費の支給申請書を提出すると、支給を受けることができます。申請時には、病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。支給されるまでに、保険診療を受けた月から少なくとも3か月程度かかります。
高額療養費の申請期限
高額療養費の申請期限は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間です。この2年以内であれば、過去の医療費についても申請して支給を受けることができます。
高額介護(介護予防)サービス費とは
高額療養費制度は医療保険の制度ですが、介護保険にも似たような高額介護(介護予防)サービス費があります。高額介護(介護予防)サービスは、介護保険を利用する際に発生する自己負担額が1か月の上限額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。この制度は、介護サービスを利用する際の自己負担を軽減するために設けられています。ただし、施設の食費や居住費、福祉用具購入費、住宅改修費、理美容代などは支給対象外です。
高額医療・介護合算制度とは
高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の自己負担額を合算し、その合計が所得区分に応じた限度額を超えた場合に、超過分を支給する制度です。この制度は、医療と介護の両方で高額な自己負担が発生する世帯の経済的負担を軽減することを目的としています。ただし、すべての自己負担額を合算できるわけではなく、すでに受け取った助成金や給付金は除外されます。高額医療・介護合算制度の計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。なお、支給額が501円以上の時に利用が可能になります。
70歳以上の方の限度額
| 適用区分 | 負担の上限額 |
| 年収約1,160万円~ | 67万円 |
| 年収約770万円~約1,160万円 | |
| 年収約370万円~約770万円 | |
| ~年収約370万円(課税所得145万円未満) | 56万円 |
| 市町村民非課税世帯 | 31万円 |
| 市町村民税非課税世帯(年金収入80万円以下等) | 19万円 ※世帯内に介護サービス利用者が複数いる場合は31万円 |
69歳以下の方の限度額
| 適用区分 | 負担の上限額 |
| 年収約1,160万円~ | 212万円 |
| 年収約770万円~約1,160万円 | 141万円 |
| 年収約370万円~約770万円 | 67万円 |
| ~年収約370万円(課税所得145万円未満) | 60万円 |
| 市町村民非課税世帯 | 34万円 |
| 市町村民税非課税世帯(年金収入80万円以下等) |
世帯に70~74歳と69歳以下の方がいる場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用します。残った負担額と69歳以下の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します。
高額医療・介護合算制度の申請方法
高額医療・介護合算制度の申請には、自宅へ申請書が届く場合と自ら申請が必要な場合があります。
高額医療・介護合算制度の申請期限
申請期限は、7月31日の翌日を起算日として2年間です。期間内であれば、過去の医療・介護費についても申請して支給を受けることができます。
使いやすさと安心を両立した訪問看護支援システム『iBow』
訪問看護支援システム『iBow』は、高額療養費や公費の自己負担額を簡単に設定でき、介護保険と医療保険の自動判定機能によって保険選択ミスを防ぐことができます。さらに社内には制度に精通したスタッフが在籍しているため、制度の見直しや変更にもスピーディーに対応。また、月1回のペースでシステム改善を行っているため、常に最新の制度に対応した状態で安心して使えます。操作もシンプルで直感的になっているためICTやシステムに不安を感じる方でも扱いやすい設計になっています。さらに、導入後はシステムの使い方だけでなく、訪問看護の制度についても気軽に相談できるカスタマーサポートも無料で利用可能です。専門のコンサルタントが丁寧に対応してくれるため、導入後も安心して活用できます。
まとめ
高額療養費制度は、医療費の自己負担額を軽減し、長期間の治療が必要な方にとって大きな支援となる制度です。訪問看護の現場では、利用者やその家族が経済的な負担に悩むケースも多く、適切な情報提供が求められます。本記事で解説した高額療養費制度の仕組みや上限額、高額介護(介護予防)サービス費、高額医療・介護合算制度を理解し、利用者が必要な支援を受けられるようサポートしましょう。訪問看護師として、医療だけでなく生活全体を支える視点を持つことで、より安心できるケアの提供につながります。
 お役立ち情報
お役立ち情報