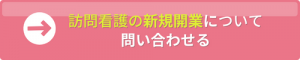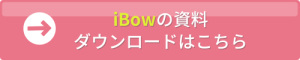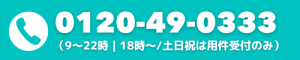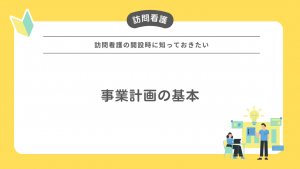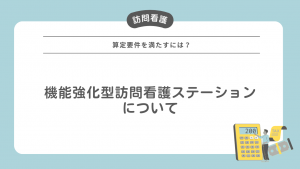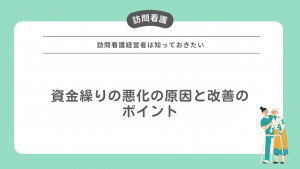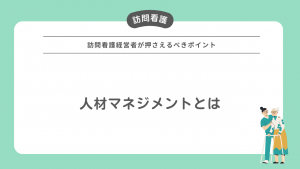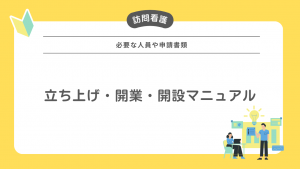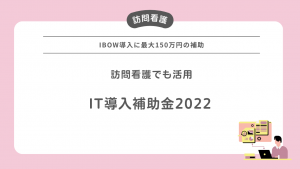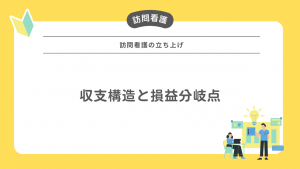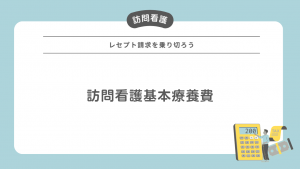訪問看護ステーション立ち上げの失敗要因とは?成功のためのポイントも詳しく解説!

高齢化による在宅医療のニーズが増加しており、訪問看護ステーションの立ち上げを検討する看護職や医療関係者が増えています。一方で、開業件数が年々増加するなか、廃業や休止に追い込まれるステーションも少なくありません。この記事では、訪問看護ステーションの開業状況とともに、経営が失敗しやすい主な要因、そして成功につなげるための具体的な対策を詳しく解説します。
訪問看護の開業状況と廃業率
全国訪問看護事業協会による令和6年度の調査によると、指定訪問看護ステーションの数は年々増加傾向にあります。 令和6年4月1日時点での全国の稼働数は17,329件にのぼり、令和5年度中に新たに開設されたステーションは2,437件。一方で、同年度中に廃止されたステーションは701件、休止されたものは291件となっています。東京都においても同様の傾向が見られ、令和6年4月1日時点の稼働ステーションは1,674件。令和5年度の新規開設は237件、廃止は75件、休止は27件でした。
立ち上げの件数が増加する一方で、一定数のステーションが廃業・休止している実態があり、訪問看護ステーションの経営には慎重な準備と運営力が求められていることが分かります。
訪問看護ステーションの経営が失敗する主な要因
訪問看護ステーションの立ち上げ数は年々増加していますが、その一方で廃業や休止に追い込まれる事業所も少なくありません。ここでは、経営が失敗する主な要因を整理し、開業前に押さえておくべきリスクを解説します。
開業準備が不十分
訪問看護ステーションの開業には、地域ニーズの調査や競合分析、サービスの差別化といった視点が必要です。しかし、勢いや理想だけで開業に踏み切り、計画段階での調査や設計が不十分なまま進めてしまうケースも少なくありません。例えば、すでに複数のステーションが密集しているエリアで開業した結果、利用者の取り合いとなり、期待していた集客がまったくできなかったという事例もあります。また、収益の柱となる医療保険・介護保険サービスのバランスや、利用者数に応じた人員配置の見通しが不十分だと、赤字経営に陥りやすくなります。開業前の段階で「どこで、どんなサービスを、誰に提供するのか」を検討することが重要です。
人手不足に陥る
訪問看護の現場では、慢性的な人手不足が深刻な課題です。特に看護師の確保は難しく、求人を出しても応募が少ない、採用してもすぐに辞めてしまうという悩みを抱えるステーションは少なくありません。常勤換算で2.5人という人員基準を下回ると、運営自体ができなくなってしまいます。さらに、教育・研修体制が整っていないと、訪問業務に不安を感じたスタッフが離職してしまうことも少なくありません。スタッフ間のコミュニケーションやサポート体制、働きやすい環境の整備は、開業後すぐに求められる経営課題のひとつです。
利用者が増えない
訪問看護ステーションの利用者は、医療機関やケアマネジャーからの紹介が多くを占めます。そのため、地域の医師、病院、居宅介護支援事業所との関係づくりができていないと、開業しても新規利用者の獲得は困難です。特に、すでにその地域に信頼関係を築いている他ステーションがある場合は、利用者を獲得するまでに時間がかかります。また、既存利用者の入院や看取りがあった場合、利用者数は減少していきます。利用者の減少を補うためにも、常に新規の利用者を確保し続けることが大切です。利用者数が伸び悩むと、固定費をまかなうことが難しくなり、経営を圧迫する原因になります。日頃から地域との関係性を深め、医療・介護関係者との信頼関係を地道に築くことが、安定経営には欠かせません。
資金繰りに行き詰まる
訪問看護は、開業してすぐに黒字化できる事業ではありません。特に新規開業の場合、利用者が増え、収益が安定するまでに一定の時間がかかります。さらに、訪問看護の報酬は、請求から実際の入金までにおおよそ2か月かかるため、開業直後は資金繰りが厳しくなりやすい傾向にあります。その間も、スタッフの人件費や車両費、事務所の家賃など固定費は継続して発生します。収支の予測や運転資金の準備が不十分なまま開業すると、数か月で資金繰りに行き詰まり、廃業となってしまう可能性もあります。開業前には、収支のシミュレーションをしっかり行い、運転資金を確保しておくことが重要です。
法律に沿った運営ができていない
訪問看護ステーションの運営には、看護師の配置基準や指定申請、主治医の指示書の管理など、医療・介護保険制度に沿った体制づくりが必要です。法律が適切に守れていない場合、行政からの指導や、悪質な場合には業務停止命令や指定取消といった重大な処分を受ける可能性があります。また、法令違反が外部に知られることで、地域や医療関係者からの信頼を失い、紹介が途絶えるなど経営にも大きな打撃を与えかねません。開業前から制度を理解し、運営開始後も法令遵守を徹底する体制を整えておきましょう。また、介護報酬は原則3年ごと、医療報酬は原則2年ごとに改定されるため、最新情報をキャッチすることも重要なポイントです。
訪問看護ステーションの立ち上げに失敗しないための対策
訪問看護ステーションの経営には、開業準備から運営体制の構築、継続的な改善まで計画性と柔軟な対応力が求められます。ここでは、立ち上げの失敗を防ぎ、安定した経営を実現するために押さえておきたい具体的な7つの対策を解説します。
1.資金計画とコスト管理を徹底する
開業資金の見積もりは必ず行い、事業計画書を作成し、収支計画・資金繰り計画を具体的な数値で立てましょう。また、訪問看護は保険請求から入金までにおおよそ2か月かかるため、その間の運転資金(給与・家賃・光熱費など)を最低でも3か月は準備しておくと安心です。資金が不足している場合は、日本政策金融公庫の融資制度や、自治体の助成金・補助金制度も積極的に活用していきましょう。資金調達についてはこちらの記事を参考にしてください。
2.地域ニーズの把握
訪問看護の需要を把握するうえで、まず重要なのが地域の人口構成、特に高齢者人口や高齢化率の把握です。高齢者が多い、または今後高齢化が進行すると見込まれる地域では、訪問看護の必要性が高まる傾向があります。市区町村が公表している要介護認定者数や、地域包括ケアに関する施策、在宅医療・介護に関する方針などの行政情報もチェックしましょう。 また、慢性疾患・精神疾患・終末期・リハビリなど、地域特有の健康課題や医療ニーズを把握することで、どのような訪問看護サービスが求められているかを具体的に検討できます。
3.競合分析
開業を検討している地域に、すでにどれだけの訪問看護ステーションが存在しているかを把握することも重要です。各ステーションが提供しているサービス内容(精神科に特化、リハビリ強化、24時間対応の有無など)や、運営母体(医療法人、社会福祉法人、大手企業、個人事業など)を調査し、自社との違いや優位性を明確にしましょう。また、競合が強みとしている領域だけでなく、逆に手薄な領域や地域で不足しているサービスがないかを分析することで、自社が提供すべき差別化ポイントを導き出すことができます。ニーズに合ったサービスを適切に提供できれば、競合の多い地域でも十分に活路を見出すことが可能です。
4.人材確保と職場環境の整備
訪問看護ステーションでは、常勤換算で2.5人以上の看護師(または保健師・准看護師)の確保が、指定申請の必須要件とされています。そのため、開業前から計画的に採用活動を行い、安定した人員体制を整えることが必要です。採用手段としては、ハローワークの活用や、看護師専門の求人サイトへの掲載が有効です。近隣のステーションが提示している求人条件も参考にしながら、自社の給与水準・勤務時間・休暇制度・福利厚生などを見直し、魅力的な条件を整えましょう。また、教育・研修体制や業務マニュアルの整備、業務報告や相談がしやすい風通しのよい職場づくりを通じて、スタッフの定着率を高める工夫も重要です。 訪問看護は一人で現場に出ることが多いため、孤立を防ぎ、悩みや不安を気軽に共有できる環境を整えることが、離職防止と安定運営につながります。
5.法令遵守
事務所や相談室の設置、感染予防設備の確保など、施設や人員に関する基準をすべて満たしているかを確認しましょう。指定申請の書類不備や、運営基準違反があると、開業後の運営指導で指摘されることや行政処分のリスクが高まります。最新の法令や報酬改定の動向をチェックし、法令遵守の意識を徹底することが重要です。訪問看護開業時の指定基準については、以下の記事を参考にしてください。
6.経営データの分析と改善
経営データの分析と改善は、訪問看護ステーションの安定運営とサービスの質を高めるために必要な取り組みです。数字に基づいて現状を把握することで、収支の安定化だけでなく、業務の効率化やスタッフの働きやすさ向上にもつながります。まず確認したいのは、収支に関する基本的なデータ(月ごとの売上高や人件費率、保険請求額と実際の入金額に差がないか、加算など)です。次に、業務効率の観点からのデータ(スタッフ1人あたりの訪問件数や移動時間の比率、書類作成にかかる時間)や、サービス利用データ(継続利用者数と新規獲得率、利用者の要介護度の分布、サービス中止の理由など)を集計すると、現場の課題が見えてきます。また、損益分岐点分析のように「黒字になるために必要な訪問件数や利用者数」を算出しておくと、経営判断に役立ちます。
7.ICTの活用による業務効率化
訪問看護では、スタッフが訪問先で過ごす時間が多く、事務所にいる時間が限られるため、記録や報告、情報共有を効率よく行える仕組みづくりが必要です。具体的には、電子カルテやモバイル端末、訪問スケジュール管理ソフト、請求業務支援ソフトなどのICTツールが有効です。ICTツールを活用することで、記録業務や事務作業の負担が大幅に軽減され、残業時間の削減にもつながります。結果として、スタッフが本来の訪問業務に集中できる環境が整い、サービスの質の向上にもつながります。
8.広報活動と営業強化
地域の中でステーションを認知してもらうためには、継続的な広報活動が欠かせません。ホームページの整備やパンフレットの作成、SNSの活用などを通じて、ステーションの特色や強みをわかりやすく発信しましょう。また、地域包括支援センターや医療機関、居宅介護支援事業所への定期訪問など、地道な営業活動も重要です。「信頼できる事業所」として地域に定着することで、紹介件数の増加が期待できます。
訪問看護の立ち上げをサポート!iBow の新規開業支援サービス
訪問看護ステーションの立ち上げを検討中の方にとって、開業準備や日々の業務など、不安や課題がつきものです。iBowの新規開業支援サービスでは、そうした課題を解消し、スムーズな運営を目指して開業準備から日々の業務までをトータルでサポートします。
1.誰でも使いやすい、直感的な操作性
iBowは、システムが苦手な方でも使いやすいシステム設計となっているため直感的な操作が可能です。また、訪問先からでもスムーズに記録ができ、帰社後の事務作業が大幅に軽減されます。テンプレート機能で記録の統一感を保ち、スタッフ間の申し送り事項も円滑に行えます。
2.どの端末でも同じ画面・同じ情報を確認
タブレット・スマートフォン・PC、どの端末からでも同じ情報にアクセスが可能です。リアルタイムで同期できるため入力のたびに操作する必要がありません。外出先や移動中も利用者情報の共有や確認ができるため、タイムロスや情報共有の漏れを防ぎ緊急訪問にもスムーズに対応できます。
3.レセプト業務を効率化して収益アップ
訪問看護ステーションの業務の中でも特に工数の大きい月初めのレセプト業務も、iBowなら記録Ⅱの内容が実績として自動反映されるため、転記の必要がありません。そのため、レセプト作成や実績との突合など作業時間や負担をグッと抑えます。今までレセプト作成や突合にかけていた時間を訪問件数の増加や営業活動に充てることで、収益の向上にもつながります。
まとめ
訪問看護ステーションの経営には、多角的な視点からの準備と柔軟な対応が求められます。失敗のリスクを減らし、安定した運営を実現するためには、立ち上げ前から具体的な計画を立て、開設後も継続的な改善を積み重ねていくことが重要です。また、地域との信頼関係を築き、スタッフが安心して働ける環境を整えることが、利用者満足と経営安定の両立につながります。
 お役立ち情報
お役立ち情報