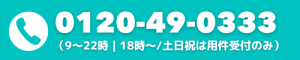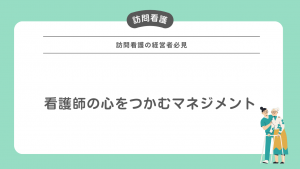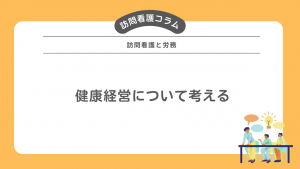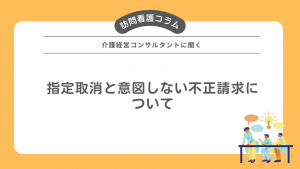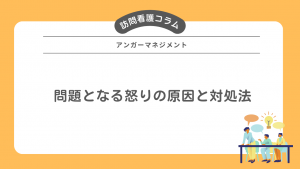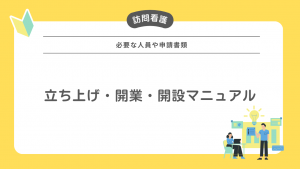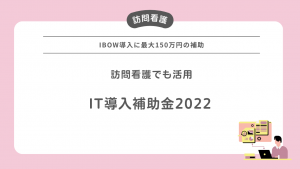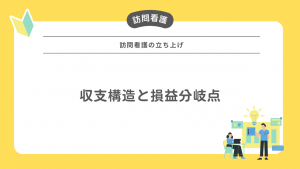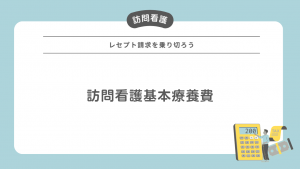介護業界最新動向14
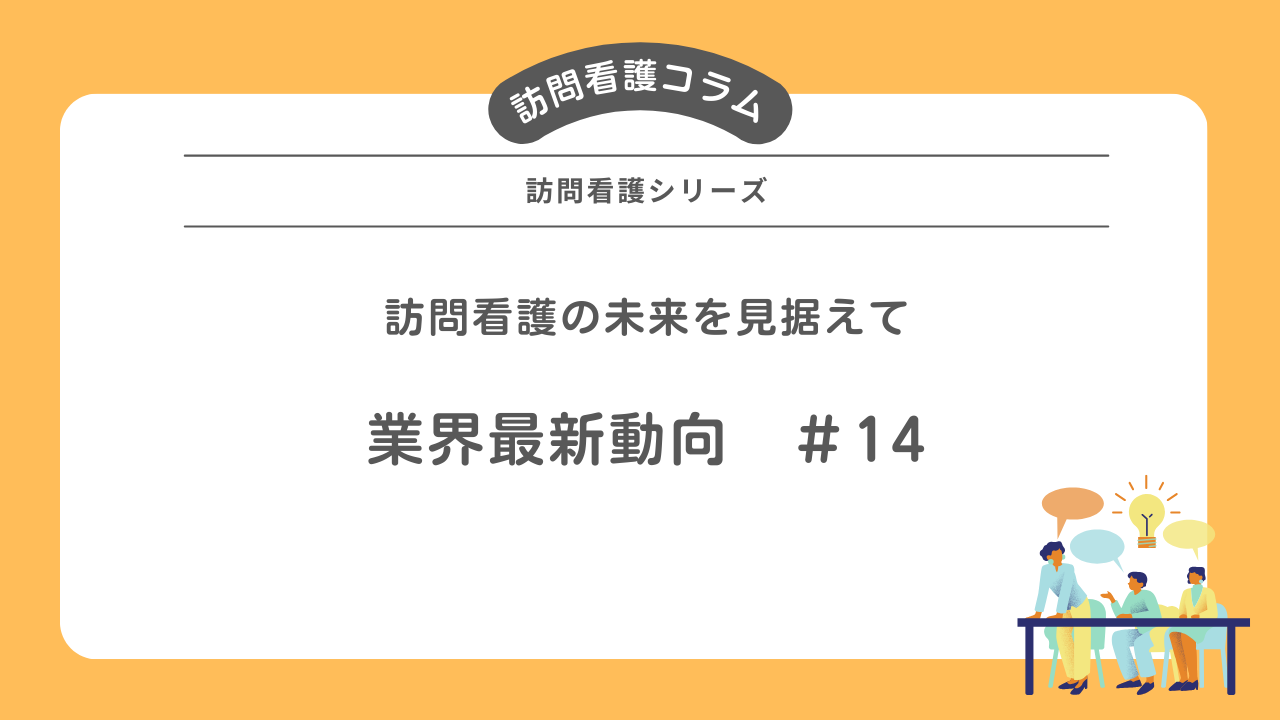
本コラムでは訪問看護業界に関わる最新の動向を探っていきます。今回は最低賃金の引き上げが訪問看護業界にあたえる影響について考えていきます。
最低賃金10月1日より63円引き上げへ 訪問看護業界へ与える影響
厚生労働省の中央最低賃金審議会は8月4日、最低賃金を63円引き上げて全国平均で時給1,118円とする目安を取りまとめました。実際の最低賃金は各都道府県が決定し、2025年10月1日から適用されます。63円は過去最大の引き上げ額となりました。また、最低賃金は2024年10月1日に50円の引き上げが行われており、2年間で113円の増額となるなど、労働者の処遇改善が急速に進んでいます。
今回は、この最低賃金引き上げが訪問看護事業経営にもたらす影響を見ていきます。
看護師は資格が必要な業務ということもあり、現在、最低賃金額で働いている人はほぼゼロかと思われます。
少々古いデータとなりますが、公益社団法人日本看護協会の「2014年訪問看護実態調査 報告書」によると、アルバイト・パートタイマーなど時給制で働く訪問看護師の平均時給は1,641円となっています。今ではもう少し上がっていると思われますし、東京や大阪などの大都市圏ではもっと高いでしょう。もともと最低賃金額を大きく上回っていますので、最低賃金が引き上げられたからといって慌てて訪問看護師の給与を上げる必要性はそれほど高くないと言えると思います。
また、現実的な問題として、介護・医療事業は国が報酬を決めており、事業者側でサービス提供価格を自由に設定できません。人件費の上昇分を価格に転嫁できないため、最低時給の引き上げに合わせて給与を柔軟に上げていくことは困難です。このため、他産業に比べると、どうしても賃金引き上げの動きは遅くなるという傾向が見られます。
この結果として、いち早く賃金引き上げを実現した他産業と訪問看護師の間の賃金ギャップが縮小します。
また、訪問看護事業所間での賃金格差も広がる可能性があります。介護報酬・診療報酬がアップしない限り、これまでと同じ売上げの中で看護師の給与引き上げを図らなくてはいけません。業務のICT化などの工夫で少ないコストで運営を行えている事業所と、そうでない事業所の間での給与格差が広がっていくことも考えられます。「高い給与水準を提示でき、優秀な人材を集められる事業所」と「給与水準が低く、人材確保に苦労する事業所」の二極化が進むのではないでしょうか。
加えて、最低賃金の引き上げは各企業の人件費の増加につながりますので、訪問看護事業所の運営に必要な製品やサービスの価格が上昇することも考えられます。例えば、今回の最低賃金引き上げとは関係ありませんが、大手携帯電話キャリアが8月20日より店頭での新規契約や機種変更をする場合の手数料を3,850円から4,950円に切り替えます。このように、特に人を介したサービスについては無料だったものが有償化されたり値上げになったりするケースが増えていくものと思われます。訪問看護事業経営への影響も決して少なくないものと思われます。
政府は労働力確保の国際的競争力の強化、長引く物価高騰の対策として「2020年代に最低時給平均1500円」という目標を立てました。その水準まであと382円です。そして2020年代に行われる最低時給の引き上げはあと4回ですから、今後は今回の63円を大きく上回るかなりの幅の引き上げが今後も続くことは容易に想像できます。この先の介護報酬・診療報酬改定の動向が不透明な中で、訪問看護事業所はそれに対応していかなくてはなりません。そのための具体的な方策としては①業務ICT化・事業所の統廃合など運営コストの削減、②保険外サービスや加算算定などの売り上げの拡大、③仕事と家庭の両立支援など給与面以外での他事業所との差別化、などが考えられます。
まとめ
価格決定を自分たちで行えない介護・医療事業者にとって、最低賃金の引き上げは経営面で大きな影響を与えることが考えられます。報酬改定の動向が不透明な中では、業務効率化などで処遇改善の原資を確保し、他産業や訪問看護業界内での人材獲得競争に打ち勝てる体制づくりが求められています。
 西岡一紀(Nishioka Kazunori) 西岡一紀(Nishioka Kazunori)フリーライター1998年に不動産業界紙で記者活動を開始。 2006年、介護業界向け経営情報紙の創刊に携わり、発行人・編集長となる。 2019年9月退社しフリー転向。現在は、大阪を拠点に介護業界を中心に新聞・会報誌・情報サイトでのインタビューやコラム執筆で活動中。 |
 お役立ち情報
お役立ち情報