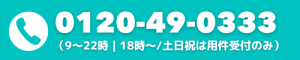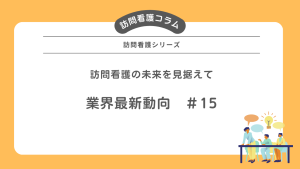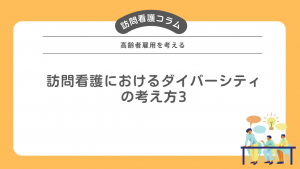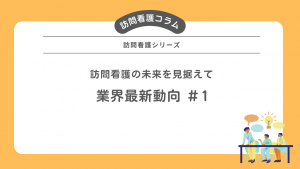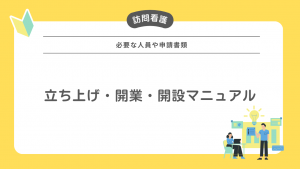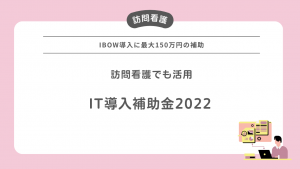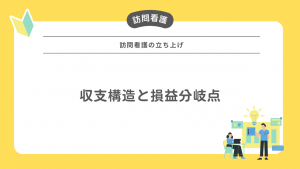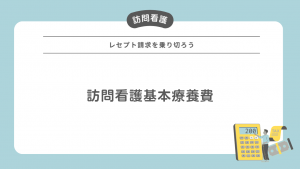訪問看護の未来を見据えて:業界最新動向#8
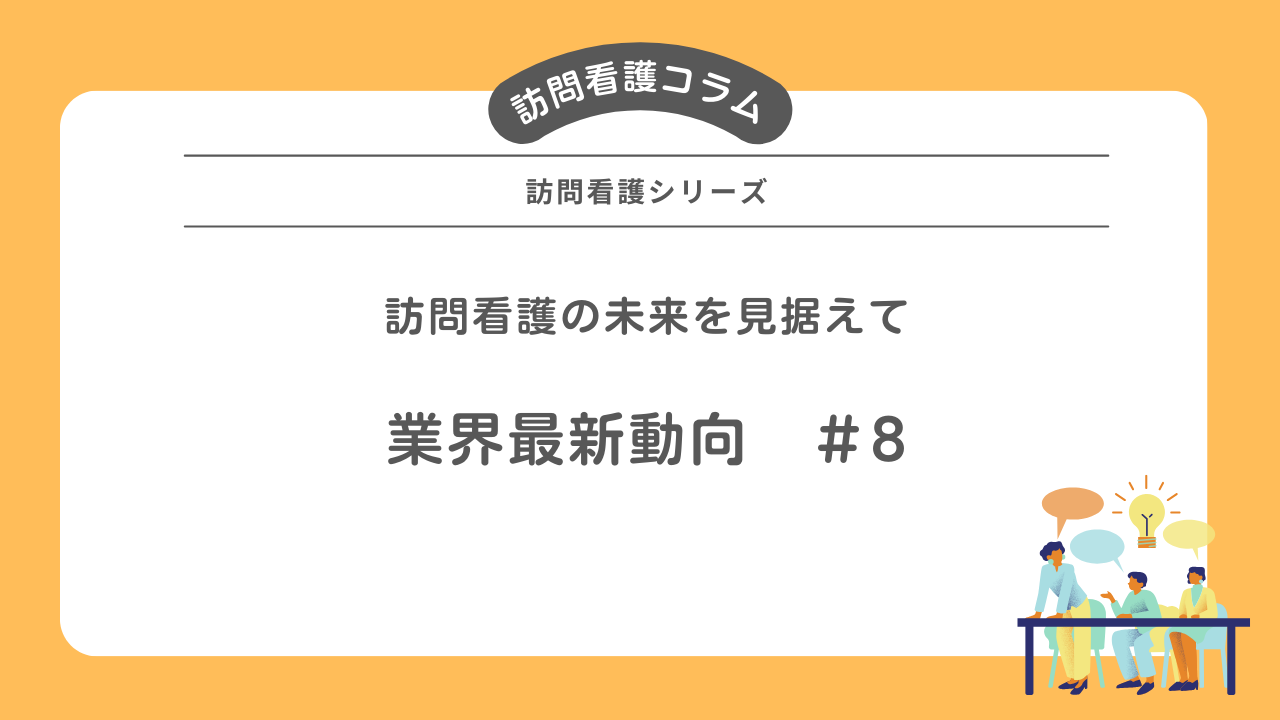
本コラムでは訪問看護業界に関わる最新の動向を探っていきます。今回のテーマは訪問看護の法定研修にも取り上げられている「感染症の予防やまん延防止のための研修」に関して取り上げます。
感染症対策研修 2割が実施不十分 訪問看護事業者も対象 運営指導時に指摘も
訪問介護事業などを手掛ける企業が、全国の医療機関・福祉施設・介護事業所に勤務する人を対象に実施した、この冬の職場での感染症の蔓延状況などに関する調査結果を2月12日に発表しました。今回は、この結果を検証してみましょう。調査は1月下旬にインターネットを通じて実施。1124人が回答しています。
質問「直近数ヶ月での勤務先における新型コロナウィルスやインフルエンザなどの感染状況」に対する回答は、「感染者無し」が最も多く36.2%。以下「数名のみの感染にとどまっている」の31.9%、「昨年末時点では感染者が多かったが今ではほとんどいない」が19.0%で、合計87.1%が、「感染状況は深刻ではない」と認識しています。では、この結果は職場全体や従業員一人ひとりの感染防止の意識の高さや実際の取り組みの効果なのでしょうか?次の質問を見てみましょう。
質問では、具体的な感染症対策を複数示し、それらについて「実施されているか」を聞きました。「あまり実施されていない」「全く実施されていない」を合計したところ、「マスクの着用」は6.6%と低かったのですが、「手洗い・手指消毒の徹底」は9.3%であり、10件に9件は実施が不十分という結果になりました。私も施設を取材で訪問していますが、以前に比べると入口で手洗いやアルコール消毒を求められるケースはかなり減ったと実感しています。同様に「定期的な換気」は14.9%、「手すり、ドアノブなど施設内の消毒」は16.4%が「実施が不十分」と回答しています。スタッフがある程度の手間や時間を割かなければいけない感染症対策については、人手不足もあり、取り組む回数や時間が減っている様子が見て取れます。
また「職員への感染症対策に関する研修の実施」は18.3%でした。2021年4月の介護報酬改定では、全サービスに感染症対策として①対策委員会の開催、②予防及び蔓延防止のための指針策定、③研修と訓練、の3点が義務化されました。3年間の経過措置が設けられていましたが2024年4月からは運営指導においても確認され、未実施の場合は行政指導の対象になります。しかし、実際には約2割の事業所がこの義務を果たしていないことがアンケートから明らかになりました。
訪問看護では、高齢者・福祉施設に訪問することも多いと思いますが、今回の結果にもあるように、それらの施設の感染症対策が不十分なケースも考えられます。訪問先でウイルスをもらってこないように、看護師自身がしっかりと対策をして訪問することが求められます。
まとめ
訪問看護事業者は、業務の特性上外部の人との接触が多く、スタッフ自身が感染する可能性が高くなります。先方の感染対策が十分でないケースも想定した上での訪問が求められます。また、訪問看護も感染対策委員会や研修は義務です。開催の証拠を自治体に示せるように、資料を作成するなどして実施しましょう。
 西岡一紀(Nishioka Kazunori) 西岡一紀(Nishioka Kazunori)フリーライター1998年に不動産業界紙で記者活動を開始。 2006年、介護業界向け経営情報紙の創刊に携わり、発行人・編集長となる。 2019年9月退社しフリー転向。現在は、大阪を拠点に介護業界を中心に新聞・会報誌・情報サイトでのインタビューやコラム執筆で活動中。 |
 お役立ち情報
お役立ち情報